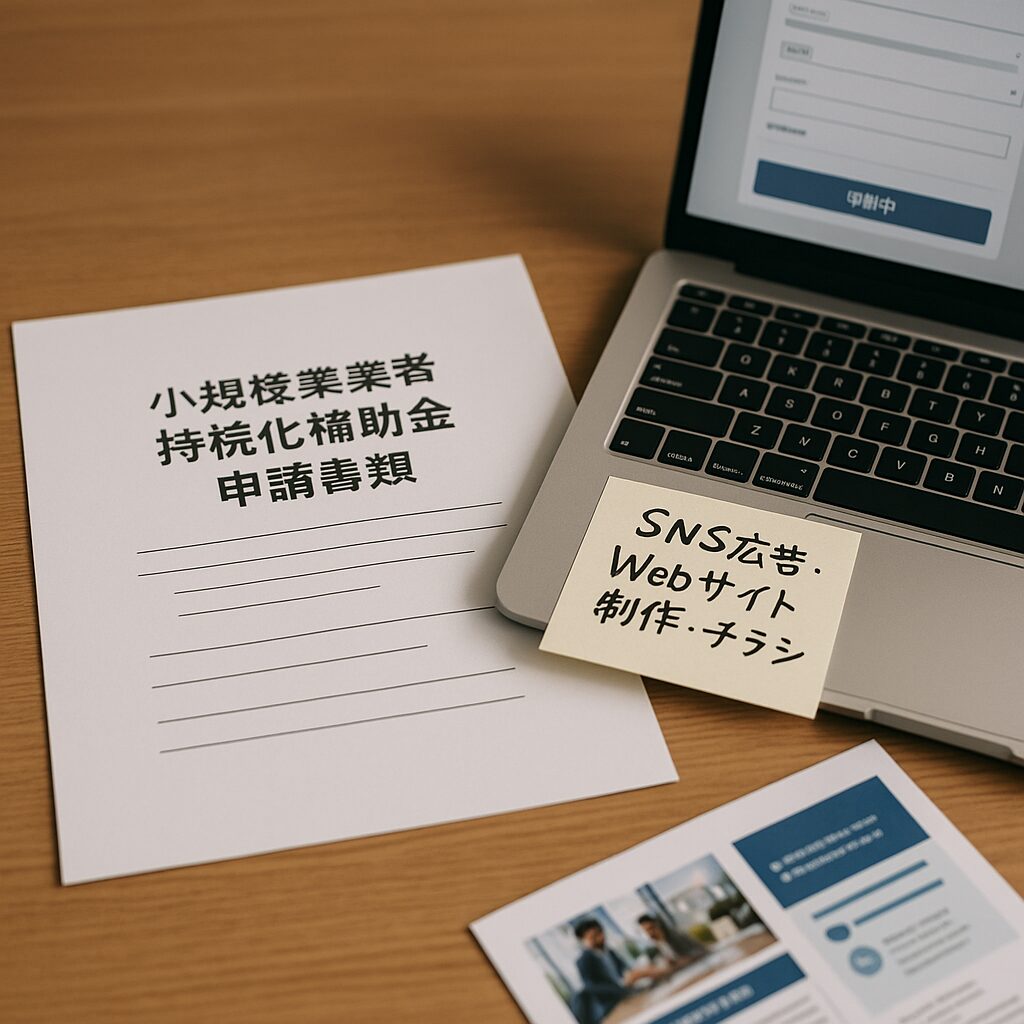「大阪・関西万博」は夕方からが本番!混雑回避・夜景満喫・イタリア館の魅力まで徹底ガイド
2025年に開催されている大阪・関西万博(EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN)。
日本で20年ぶりに開催されるこの大規模国際博覧会は、世界中から注目を集めています。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。万博記念公園とは異なる舞洲(夢洲)の特設会場での開催は、未来都市のような風景と先端技術の融合を感じさせます。
そんな万博、私は最近“夕方から夜にかけての訪問”という楽しみ方を体験しました。
結論から言うと……大正解でした。
この記事では、夕方〜夜間に行くメリットと、現地で見逃せないイタリア館などのおすすめスポット、混雑・天候への対応策をまとめます。
■ 夕方〜夜に訪れるメリット5選
① 混雑がグッと減る
午後4時を過ぎた頃から、昼間に訪れた人たちが退場し始めます。
特に平日は顕著で、18時以降は主要パビリオンの待ち時間が激減。
中には、午前中は60分待ちだったパビリオンが、夜には5〜10分で入れたものもありました。
② ライトアップされた幻想的な夜景
万博会場の建築は、夜になると別世界。
ライトアップによる照明演出や、LEDスクリーン、AR演出などが一斉に輝き出し、フォトスポットとしても魅力倍増します。
SNS投稿用の“映え写真”を撮るなら、断然夜です。
③ 気温が下がって快適
日中は暑さと照り返しでかなり体力を奪われますが、夕方以降は風が出て涼しくなります。特に夏場は、夜のほうが屋外移動がずっと楽です。
④ チケット代がお得な時間帯もある
公式サイトでの購入時には、夕方〜ナイトパスのような時間制料金が出てくる場合も。混雑も避けられて、料金もお得という理想的なプランです。
⑤ 帰宅ラッシュを回避できる
閉場の21:00までゆっくり楽しんだあと、逆方向の電車で帰ると、一般の帰宅ラッシュを避けてスムーズに帰れます。
■ パビリオン巡りで外せない「イタリア館」
訪問前にSNSで「イタリア館は絶対行って!」という声をよく目にしました。
実際に行ってみると、その理由がよくわかりました。
イタリア館は、建築デザインから展示演出までが洗練されており、
中では伝統工芸とデジタルアートが融合したインスタレーションが展開されています。
光、音、映像を駆使した空間の中に身を置くと、“体験型アートミュージアム”に来たような感覚になります。
スタッフの対応も丁寧で、英語・日本語両方に対応。
混雑時間を避けて訪れると、じっくりと堪能できます。
■ 雨天を避けるなら“天気+混雑”を事前チェック
万博は屋外移動が基本なので、雨の日はレインコート&長靴が必須。
正直、快適とは言えない日もあります。
おすすめは以下の3点:
- 公式アプリで混雑・天気をチェック
- チケットは事前予約し、キャンセル可能な日を選ぶ
- 前日の天気予報で判断し、晴れた日に振り替える
■ 夕方以降のモデルプラン(所要約4時間)
| 時間帯 | 行動 |
|---|---|
| 16:00 | 万博会場到着・入場ゲート通過 |
| 16:30 | 人気パビリオン(イタリア館など)へ直行 |
| 18:00 | 軽食&休憩。グルメブースで万博限定メニューを楽しむ |
| 18:30 | ライトアップ開始。夜景フォトタイム |
| 19:00 | もう2〜3ヶ所パビリオン巡り |
| 20:30 | お土産購入・夜景を見ながら退場 |
■ おすすめの持ち物(夕方〜夜の来場用)
- モバイルバッテリー(公式アプリ・AR体験など電池消費大)
- 羽織る上着(夜は肌寒い日も)
- QR付きチケット(スマホでOK)
- カメラ(スマホでもOKだが、夜景は高画質が映える)
- 軽めの折りたたみ傘(晴れていても突然の通り雨に備える)
■ 万博の魅力は“人混み”だけじゃない
確かに「人が多い」というイメージが先行する万博ですが、
時間帯や曜日、天気を味方につければ、静かでゆったりした万博体験が可能です。
訪れる前の準備と工夫で、何倍も楽しめる空間がそこにはあります。



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=21541214&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5339%2F9784835645339_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)