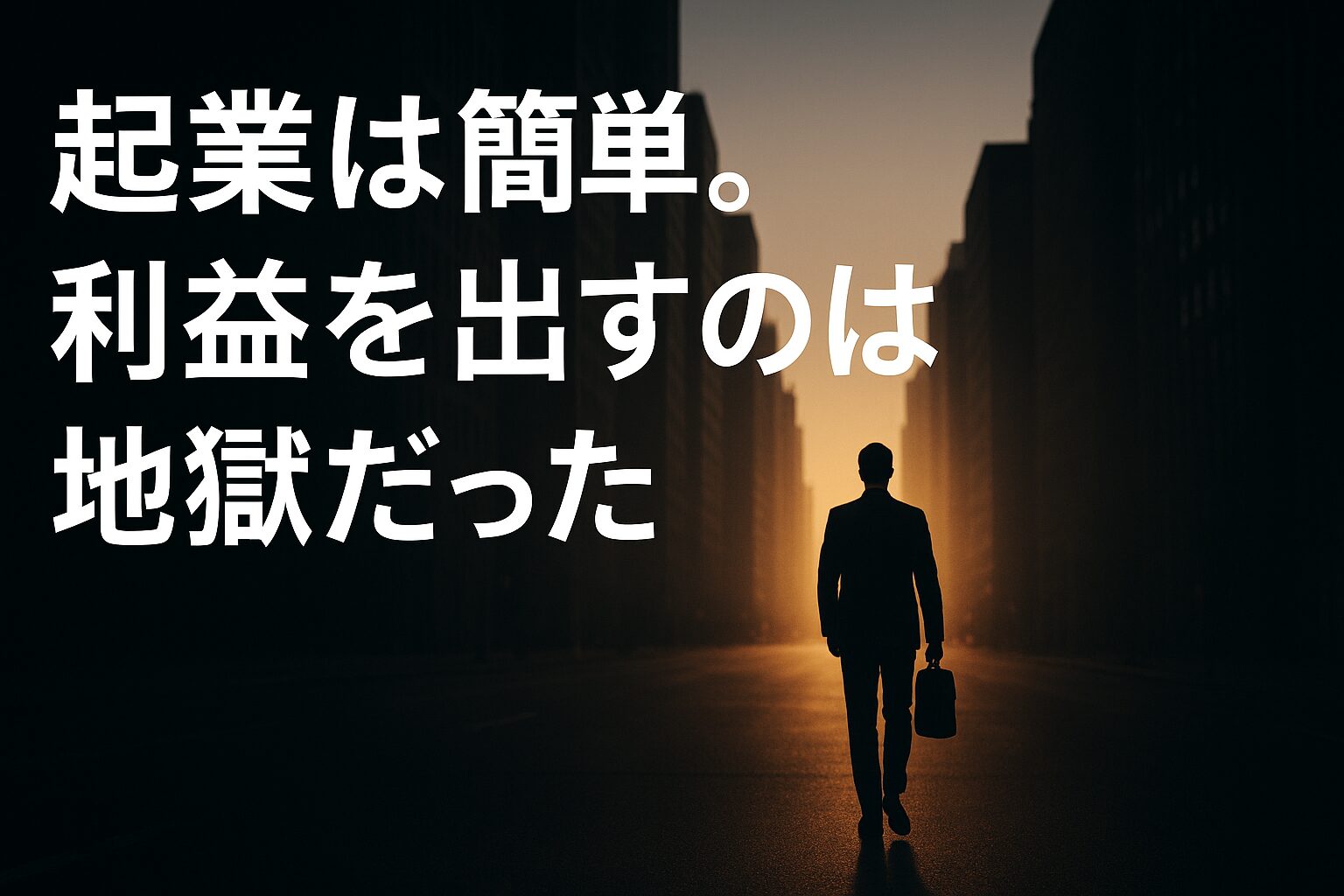🏷 カテゴリ
社会・メディア批評・ジェンダー・表現論・思考の整理
✍️ 本文
序章:「性加害」という言葉のもやもや
昨日、NHKスペシャル「(性)加害の扉を開くとき」を見た。
タイトルからして重く、社会的に重要なテーマであることは分かる。だが、番組を最後まで見ても──正直なところ「何を言いたかったのか」がよく分からなかった。
番組は“性加害”という言葉を繰り返し使いながら、被害者と加害者、社会の意識、そして日本社会の沈黙について語ろうとしていた。
だが、私の中にはひとつの強い違和感が残った。
「“性加害”って、具体的に何を指しているのか?」
という点である。
第一章:「性加害」という言葉が生んだ霧
ここ数年、メディアや行政、教育の場で「性加害」という言葉が急速に広まった。
だが、その中身は曖昧だ。盗撮、痴漢、性的暴行、セクハラ──すべてが「性加害」という一言でまとめられてしまう。
それはまるで、すべての「暴力」を“暴力”という単語一つで語るようなものだ。
殴打も、虐待も、戦争も、いっしょくたにして「暴力」と呼んだら、本質は見えなくなる。
この番組も、まさにその罠に陥っていたように思う。
加害の構造を語ると言いながら、個別の加害行為を具体的に描かず、抽象的な“反省”と“対話”の言葉だけが宙を舞っていた。
第二章:誰が語り、誰が沈黙しているのか
番組のディレクターは何年も取材を重ねたという。
だが、長期取材の重みよりも、編集された言葉の“慎重さ”ばかりが目立った。
慎重であることは大事だ。だが、その慎重さが**「何も言わない」こと**と紙一重になる瞬間がある。
加害者を「性加害者」とひとくくりにするとき、その中には盗撮の加害もあれば、暴行やレイプといった犯罪も含まれる。
社会的制裁の重さ、被害の深さ、回復の道──すべてが異なるのに、
“性加害”という言葉に包まれた瞬間、差が消える。
その曖昧さが、むしろ問題の本質を覆い隠してしまう。
第三章:言葉が失われるとき
「言葉を選ぶこと」は、報道や表現の根幹だ。
しかし、“性加害”という語の登場以降、日本のメディアでは「直接的な言葉」を避ける傾向が加速している。
“レイプ”と言わない。
“強制わいせつ”とも言わない。
ただ「性加害」と言う。
それは視聴者に“想像の余地”を残すという建前かもしれない。
だが実際には、“想像”ではなく“混乱”を生む。
具体性を失った言葉は、現実をぼかす。
そして、ぼかされた現実の中で、誰かが再び傷つく。
第四章:本当に伝えるべきこととは何か
社会に必要なのは「性加害は悪い」という当たり前の再確認ではない。
必要なのは、**「どのような行為が、どのようにして起こるのか」**を具体的に理解することだ。
それによって、初めて予防や教育、被害者支援の道が見えてくる。
「性加害はいけない」という言葉は正しい。
だが、それだけでは何も変わらない。
「では、どんな行為がそうなのか」「どうすれば止められるのか」を語らなければならない。
番組が“加害の構造”を扱うなら、そこにこそ焦点を当てるべきだった。
しかし、実際は“反省”というモラルの枠組みの中で、安全な言葉だけが選ばれていた。
第五章:「言葉の責任」と「視聴者の思考」
視聴者としての私たちにも、責任がある。
メディアがぼかした言葉を使うとき、私たちはその曖昧さに安堵してしまう。
「直接的すぎるのはちょっと…」という感情の背後には、社会全体の“見たくない”という無意識の同調がある。
だが、曖昧な言葉は、被害者にも加害者にも冷たい。
どちらに対しても、理解を深める道を閉ざしてしまう。
終章:「性加害」という言葉を問い直す
NHKスペシャル「性加害の扉を開くとき」は、確かに勇気ある企画だ。
だが、その勇気をもう一歩先に進めてほしかった。
「性加害」という言葉の“扉”を開くのではなく、
**「具体的な現実」**の扉を開くこと。
それこそが、社会が本当に必要としている報道のあり方ではないだろうか。
ブラウザだけでできる 本格的なAI画像生成 【ConoHa AI Canvas】NHKスペシャル『性加害の扉を開くとき』を見て思う。──“性加害”という曖昧な言葉が、議論を止めている
🏷 カテゴリ
社会・メディア批評・ジェンダー・表現論・思考の整理
✍️ 本文
序章:「性加害」という言葉のもやもや
昨日、NHKスペシャル「(性)加害の扉を開くとき」を見た。
タイトルからして重く、社会的に重要なテーマであることは分かる。だが、番組を最後まで見ても──正直なところ「何を言いたかったのか」がよく分からなかった。
わざわざ見る価値は正直なかった。
番組は“性加害”という言葉を繰り返し使いながら、被害者と加害者、社会の意識、そして日本社会の沈黙について語ろうとしていた。
だが、私の中にはひとつの強い違和感が残った。
「“性加害”って、具体的に何を指しているのか?」「何故どんな加害が明確にして区別しないのか」
という点である。
第一章:「性加害」という言葉が生んだ霧
ここ数年、メディアや行政、教育の場で「性加害」という言葉が急速に広まった。
だが、その中身は曖昧だ。盗撮、痴漢、性的暴行、セクハラ──すべてが「性加害」という一言でまとめられてしまう。
それはまるで、すべての「暴力」を“暴力”という単語一つで語るようなものだ。
殴打も、虐待も、戦争も、いっしょくたにして「暴力」と呼んだら、本質は見えなくなる。
この番組も、まさにその罠に陥っていたように思う。
加害の構造を語ると言いながら、個別の加害行為を具体的に描かず、抽象的な“反省”と“対話”の言葉だけが宙を舞っていた。
第二章:誰が語り、誰が沈黙しているのか
番組のディレクターは何年も取材を重ねたという。
だが、長期取材の重みよりも、編集された言葉の“慎重さ”ばかりが目立った。
慎重であることは大事だ。だが、その慎重さが**「何も言わない」こと**と紙一重になる瞬間がある。
加害者を「性加害者」とひとくくりにするとき、その中には盗撮の加害もあれば、暴行やレイプといった犯罪も含まれる。
社会的制裁の重さ、被害の深さ、回復の道──すべてが異なるのに、
“性加害”という言葉に包まれた瞬間、差が消える。
その曖昧さが、むしろ問題の本質を覆い隠してしまう。
第三章:言葉が失われるとき
「言葉を選ぶこと」は、報道や表現の根幹だ。
しかし、“性加害”という語の登場以降、日本のメディアでは「直接的な言葉」を避ける傾向が加速している。
“レイプ”と言わない。
“強制わいせつ”とも言わない。
ただ「性加害」と言う。
それは視聴者に“想像の余地”を残すという建前かもしれない。
だが実際には、“想像”ではなく“混乱”を生む。
具体性を失った言葉は、現実をぼかす。
そして、ぼかされた現実の中で、誰かが再び傷つく。
第四章:本当に伝えるべきこととは何か
社会に必要なのは「性加害は悪い」という当たり前の再確認ではない。
必要なのは、**「どのような行為が、どのようにして起こるのか」**を具体的に理解することだ。
それによって、初めて予防や教育、被害者支援の道が見えてくる。
「性加害はいけない」という言葉は正しい。
だが、それだけでは何も変わらない。
「では、どんな行為がそうなのか」「どうすれば止められるのか」を語らなければならない。
番組が“加害の構造”を扱うなら、そこにこそ焦点を当てるべきだった。
しかし、実際は“反省”というモラルの枠組みの中で、安全な言葉だけが選ばれていた。
第五章:「言葉の責任」と「視聴者の思考」
視聴者としての私たちにも、責任がある。
メディアがぼかした言葉を使うとき、私たちはその曖昧さに安堵してしまう。
「直接的すぎるのはちょっと…」という感情の背後には、社会全体の“見たくない”という無意識の同調がある。
だが、曖昧な言葉は、被害者にも加害者にも冷たい。
どちらに対しても、理解を深める道を閉ざしてしまう。
終章:「性加害」という言葉を問い直す
NHKスペシャル「性加害の扉を開くとき」は、確かに勇気ある企画だ。
だが、その勇気をもう一歩先に進めてほしかった。
「性加害」という言葉の“扉”を開くのではなく、
**「具体的な現実」**の扉を開くこと。
それこそが、社会が本当に必要としている報道のあり方ではないだろうか。


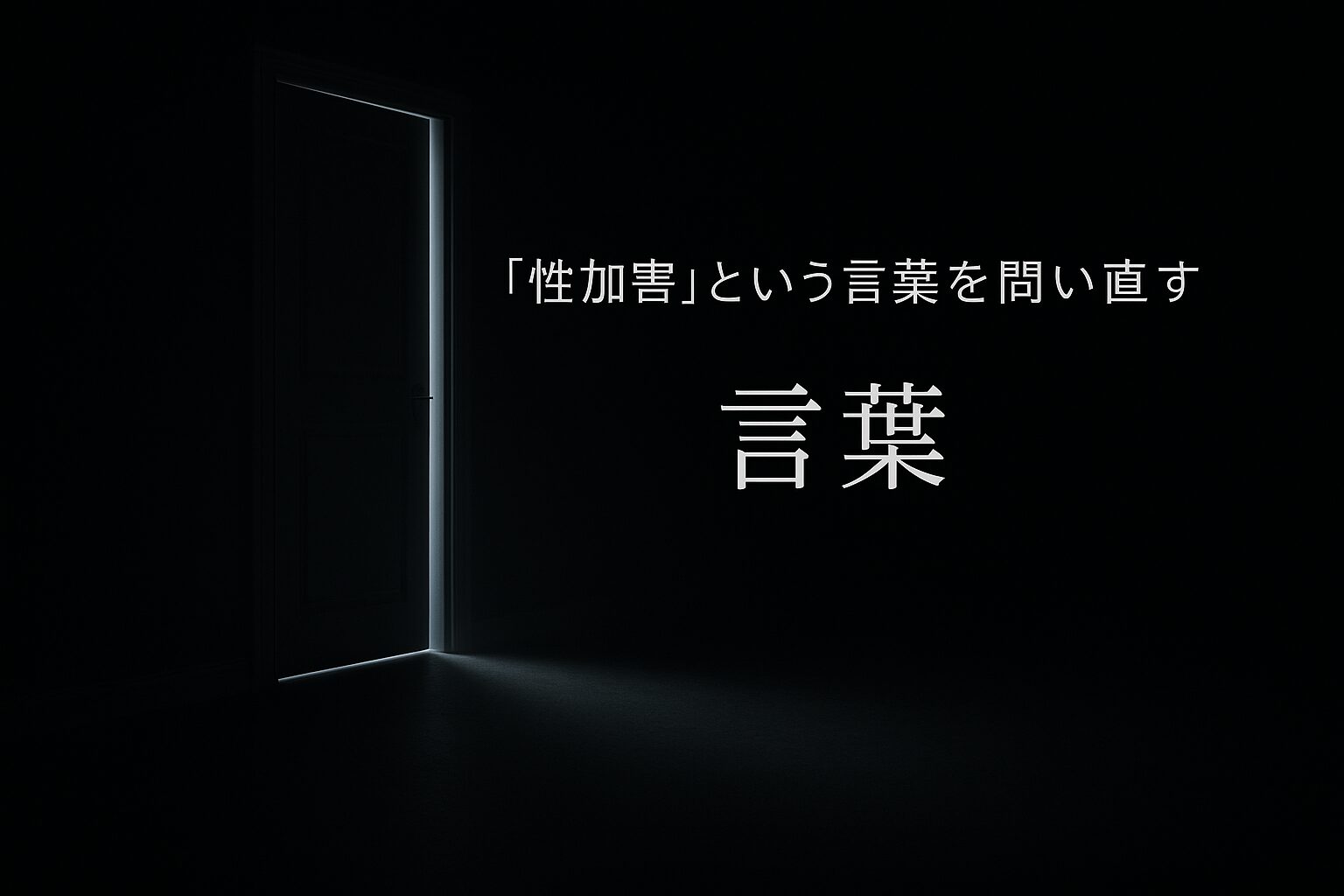
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=21435533&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4569%2F9784797674569_1_48.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)