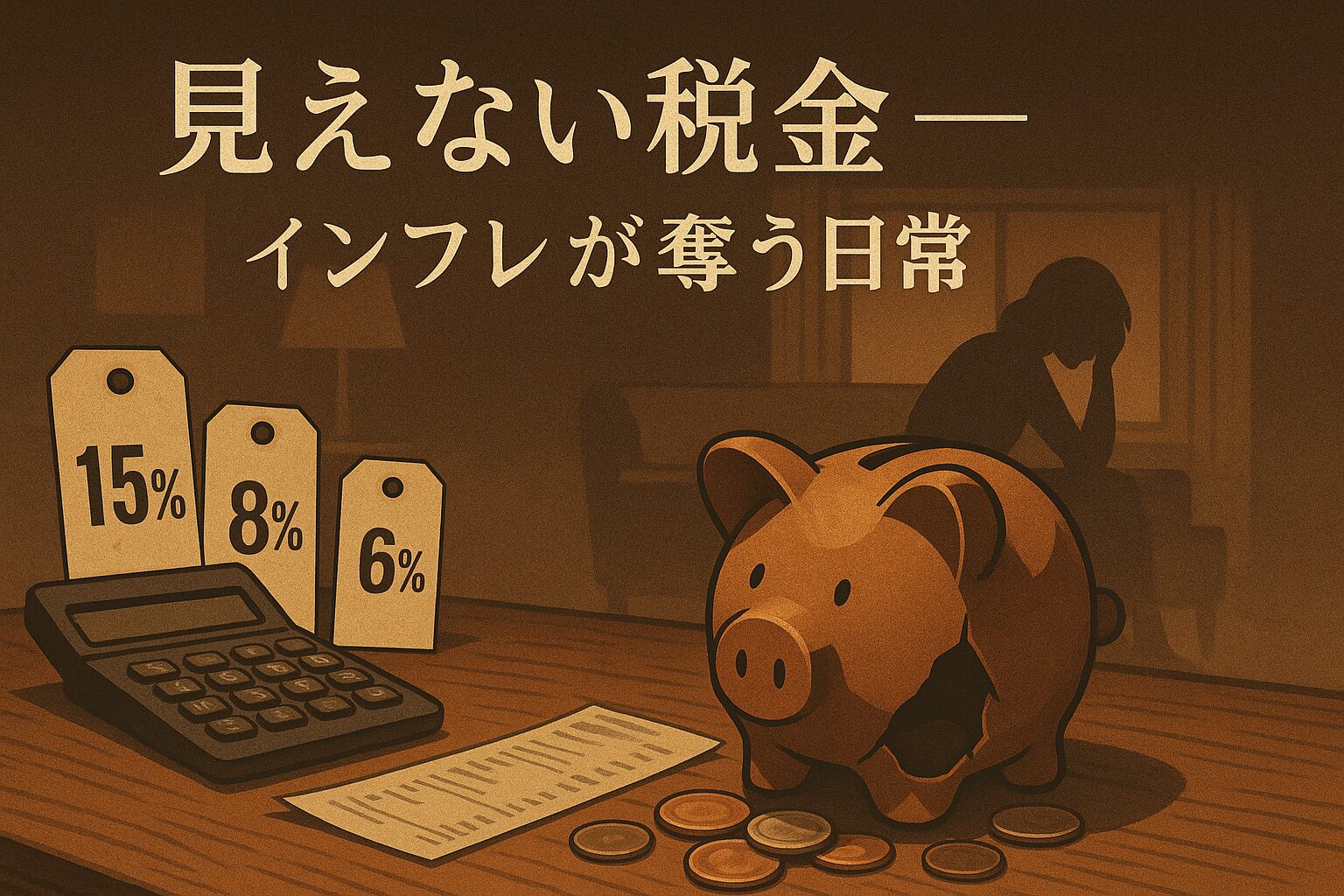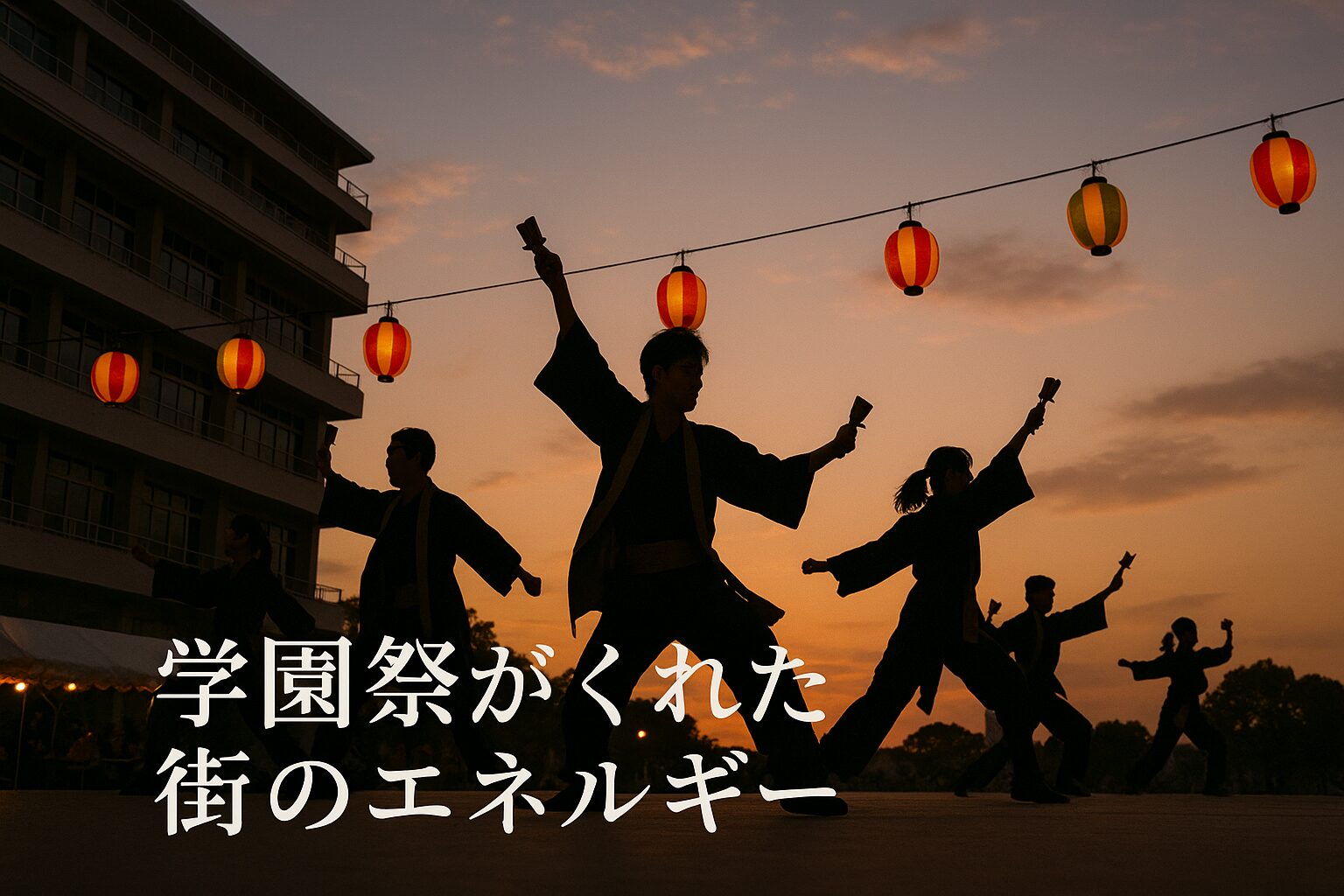🚗「止められない車」が社会の盲点に?
アクセルとブレーキの踏み間違い事故の実態と、“今どき止まらない車”への問題提起
カテゴリ:社会・安全・交通
序章:「また踏み間違い事故」― それ、本当にドライバーだけの責任ですか?
ニュースで「アクセルとブレーキの踏み間違い事故」を見ない週は、ほとんどありません。
「高齢者がまた」「運転ミスが原因」といった報道が繰り返されるたび、
私たちは“運転者個人のミス”として処理していないでしょうか?
しかし私は思います。
―― 今どき止められない車の方が悪いのでは?
テクノロジーがこれだけ進化した時代に、
誤ってアクセルを踏んでも止まらない、暴走を防げない車がまだ多数走っている現実。
それを「人間のミス」で片付けてよいのか。
この構造こそ、社会全体で見直すべきだと感じています。
第1章:踏み間違い事故の実態 ― 数字の裏にある「設計の遅れ」
交通事故総合分析センター(ITARDA)の報告によれば、
2018~2020年の3年間で「踏み間違い」による死傷事故は 9,738件。
1年あたりおよそ 3,000件以上。
その多くが「駐車場」や「発進時」などの低速走行時に発生しています。
そして、75歳以上の高齢者が関係するケースが約2,000件を超える一方、
24歳以下の若者も1,600件以上を起こしているのが現実です。
この数字が意味するのは――
ヒューマンエラーは年齢を問わず発生するという事実。
そして、その「エラーを検知し、止められない車」がまだ道路上にあふれているという現状です。
第2章:「止められない車」が存在する理由 ― 技術より“コスト”を優先?
2025年にもなろうというこの時代、
誤発進抑制や自動ブレーキ、前後障害物検知は決して珍しい技術ではありません。
むしろ、**“搭載していないこと自体がリスク”**です。
しかし現実には、こうした装備は今なお「上位グレード限定」「オプション扱い」という車が多数。
軽自動車・コンパクトカーなど、普及台数の多いカテゴリーほど装備率が低い傾向にあります。
“命を守る装備が、グレード次第でつけられない”
― この構造そのものが、社会的な盲点ではないでしょうか。
私たちはこれを、「ドライバーのミス」と呼ぶことで、
実はメーカーの設計思想の遅れを見逃しているのかもしれません。
第3章:最新車の「止まる力」と旧世代車の「止まらなさ」
ここで比較してみましょう。
| 区分 | 主な安全装備 | 誤発進・踏み間違い時の動作 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 最新モデル(2022年以降) | 自動ブレーキ+誤発進抑制+障害物検知 | 加速前にエンジン出力をカット。障害物検知で自動ブレーキ作動 | コンビニ突入事故をほぼ防止 |
| 2010年代中期車両 | 自動ブレーキは前方のみ | 前進時のみ対応、後退では暴走の可能性あり | 駐車場事故が多発 |
| 2000年代以前 | 安全装備なし | 誤発進を検知せず、全開加速 | 高齢者が多く使用中 |
この比較を見ると、明らかに“技術的な差”が事故率を左右していることがわかります。
つまり、「止められない車」が事故を起こし、「止められる車」が事故を防いでいる構図です。
第4章:それでも“ドライバーの責任”で片付ける社会
踏み間違い事故が起こるたび、
「高齢者は免許を返納すべき」「注意不足が原因」などの論調が巻き起こります。
しかし、もしその車に自動停止装置がついていれば、
アクセルを踏み間違えても暴走は防げたかもしれません。
それなのに社会は「操作ミス」と切り捨て、
メーカーは「装備はオプションです」と言い逃れる。
技術的に止められるのに、止めないまま販売している。
これは**“構造的な怠慢”**といえるのではないでしょうか。
第5章:車種・グレード公開の意義 ― 責任を「見える化」するために
私は、事故が起きた際に「車種・グレードを公開すべき」と考えています。
それは、犯人探しではなく、安全性の可視化のためです。
- どの車がどの安全装備を搭載していたのか
- 発生した事故の多くが“安全装備非搭載車”だったのか
- グレード間でどれほどの安全性能差があるのか
これを明示することで、メーカーも消費者も正しい判断ができる。
「買う人が安全を選べる社会」に変えていけるのです。
第6章:メーカー・行政が今すぐ取り組むべきこと
- 全車種に誤発進抑制を標準装備化
軽自動車や旧世代モデルにも後付け対応を。 - 装備有無を義務的に開示
「安全装備なし車」を販売する際は、明示的な説明を義務づける。 - 事故統計の透明化
車種・グレード別の安全性データを公的に公開し、社会的検証を可能にする。 - 自治体の補助制度
誤発進防止装置の後付けに補助金を出すなど、実効的対策を広げる。
第7章:ドライバーができる、自分と家族を守る意識改革
- 「止められない車」に乗っている自覚を持つ
- 安全装備がない車は“操作で補う”しかないと認識する
- 家族の車にも安全機能があるかを確認する
- 高齢の親に、買い替え・機能追加を提案する勇気を持つ
結論:止まる車が“標準”になる社会を
「止まらない車を止める技術」は、すでに存在します。
問題は、それを“すべての車に搭載する社会的意思”があるかどうかです。
ドライバーにだけ責任を押しつけるのはもうやめましょう。
テクノロジーが人の命を守る時代に、止められない車を走らせている社会の方が遅れているのです。



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=20892763&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8478%2F9784761528478_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)