ドル基軸体制の揺らぎと日本の選択肢:日銀・FRBの政策が鳴らす新時代の鐘
カテゴリ:国際経済、中央銀行政策、金融市場
はじめに:静かに崩れ始めた世界の金融秩序
2025年の夏、世界の金融市場は一見すると平穏を保っているように見える。しかし、よく目を凝らしてみれば、その根底には大きなうねりが存在している。日銀の量的緩和政策を通じた海外資産の買い入れ、特に米国株や米国債への過剰な資金供給は、日米両国で「すべてがバブル(Everything Bubble)」と呼ばれる異常な資産インフレを招いた。そして今、そのつけが一気に表面化しつつある。
私たちは今、「ドル基軸通貨体制」という長年の国際金融の礎が、静かに揺らぎ始めている歴史的瞬間に立ち会っているのかもしれない。
第1章:日銀の量的緩和とバブルの構造
2013年にスタートした日銀の量的・質的緩和(QQE)は、名目GDPや物価上昇率に一定のプラス効果を与えたものの、それ以上に副作用も大きかった。超低金利・資産買い入れ政策によって生み出された潤沢な資金は、円キャリートレードを通じて海外市場に流れ込み、特に米国の株式市場や債券市場を押し上げる原動力となった。
世界経済は、かつてないほど金融政策に依存した形で均衡を保ち、中央銀行が事実上の株主のように振る舞う「国家資本主義」の様相を呈している。
第2章:ドル基軸通貨体制の地殻変動
国際通貨基金(IMF)の統計によれば、各国中央銀行の外貨準備に占める米ドルの割合は、1999年の約71%から2021年には59%にまで低下している。また、米ドル建ての債務や取引の割合も徐々に減少し、中国を中心とした脱ドル化(ディドラー)の動きが着実に進行中である。
人民元建てのステーブルコインの構想や、BRICS諸国による非ドル決済プラットフォームの模索は、これまでの一極通貨体制から多極化した通貨秩序への移行を象徴している。
とはいえ、依然としてドルは外国為替市場の88%に関与し、事実上の「世界の通貨」であることに変わりはない。この「揺らぎ」はまだ初期段階に過ぎないが、それが確実に進行していることは否定できない。
第3章:トランプ政権とFRBの異常な関係
米国大統領選を前にして再び台頭してきたドナルド・トランプ氏は、前回政権時同様にFRB(連邦準備制度)に対して強硬なスタンスを見せている。利上げ局面ごとに政権が過剰な介入を行い、「正常化」を阻止するような構図が繰り返されてきた。
仮に今後、米国経済が景気減速を受けてFRBが利下げに転じれば、それは日本にとって重大な転機となる。なぜなら同時に、日銀が金利引き上げに動けば、これまでの資金フローが逆流し、円キャリートレードの巻き戻しによって世界の市場が大きく揺れるからだ。
第4章:日銀の利上げ、FRBの利下げがもたらす鐘の音
日本銀行は、2024年に17年ぶりとなる政策金利の引き上げに踏み切った。この動きは、一見すると遅きに失した対応に見えるかもしれないが、同時に金融の流れを大きく変える起点でもある。
一方、インフレ率の鈍化を受けてFRBは今後利下げに転じる可能性がある。すると、日米の金利差は縮小し、これまで米国資産に向かっていた日本マネーが自国回帰する流れが強まるだろう。
これは単なる市場変動ではなく、「新しい時代の鐘の音」である。
第5章:日本の未来、そして世界の行方
日本にとって最大の懸念は、金利上昇が財政を直撃するという現実である。国債費(利払いと償還)に年間30兆円超が必要とされる中、利回り上昇はそのまま財政負担の増加に直結する。
しかし、見方を変えれば、これは「金利のある正常な世界」への回帰とも言える。ゼロ金利と緩和依存からの脱却こそ、真の健全化への一歩なのだ。
そして国際社会に目を向ければ、ドル一極集中から、複数の通貨が共存する「多極的通貨秩序」へと移行する可能性が見えてくる。円、ユーロ、人民元、そして金。多様な通貨の中で、安定と信頼を得る国だけが新しい秩序の担い手となる。
おわりに:世界が幸せであるために
あなたが最後に述べた「世界が幸せになりますように」という願い。それは私たちすべてにとって普遍的な希望だ。
その実現には、単なる金融政策の調整を超えた、信頼・公平性・国際協調の再構築が必要である。どれほど経済が成長しても、社会に分断と不平等が広がるようでは意味がない。
今こそ、「金融」「通貨」「政策」という無機質な言葉の背後にある、人間の幸せという原点に立ち返るべきときである。


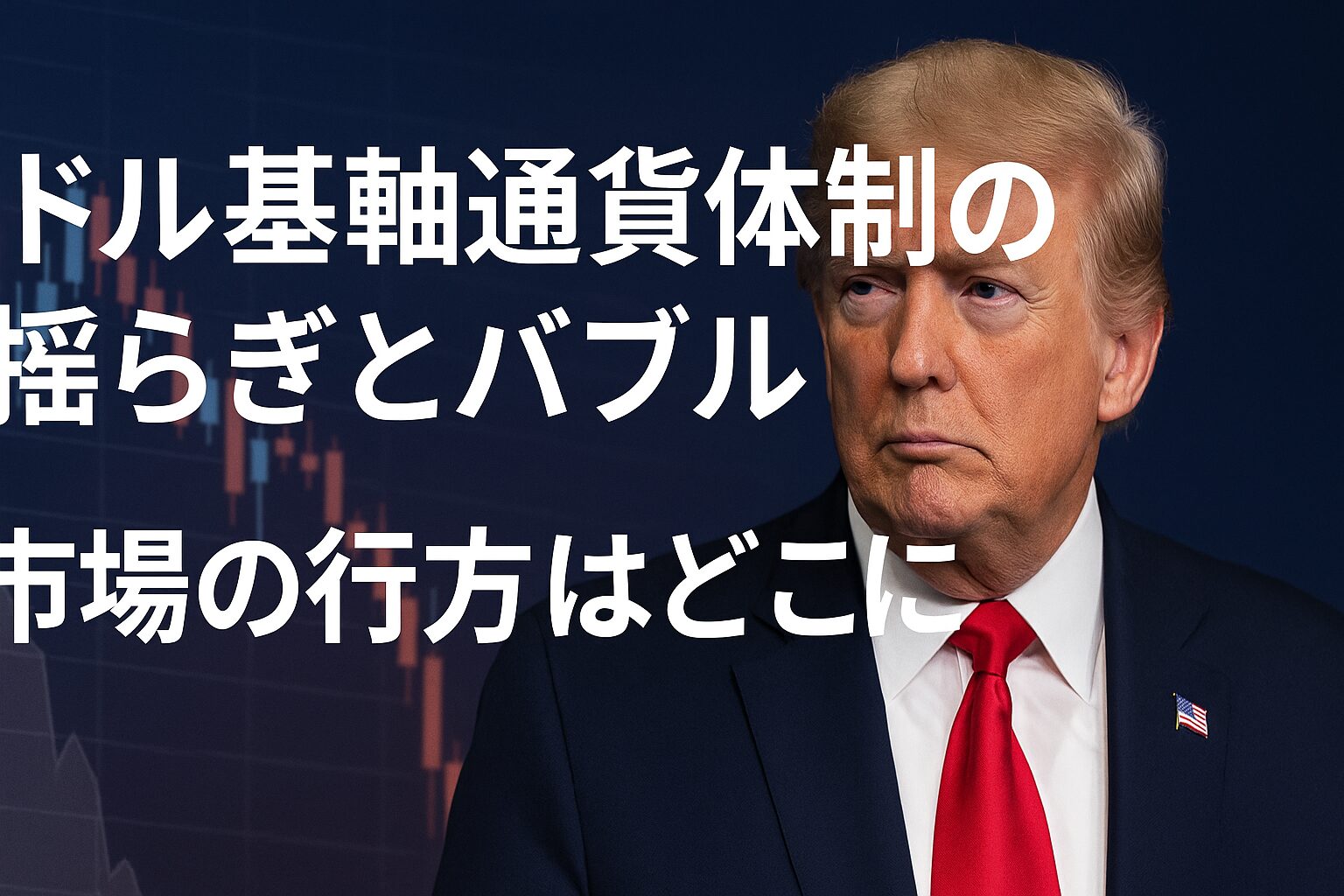
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=21593687&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1402%2F9784087861402_1_39.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


