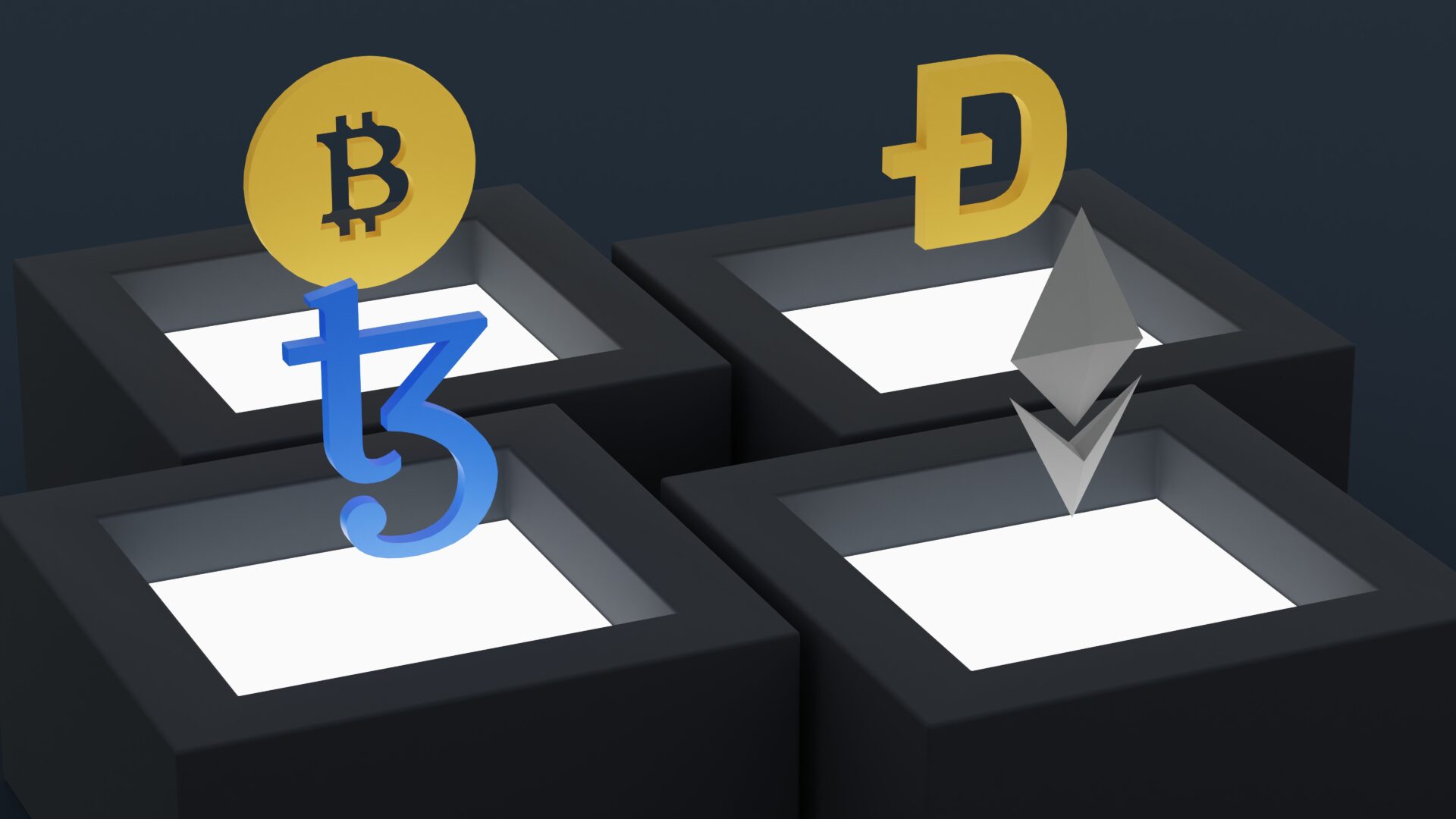ビジネス契約書について、お話を聞いてきました。
地味だけど、とても重要な内容だと認識しました。
どんなに議論経緯があったとしても、結果は最終のビジネス契約書が全て。裁判所は、ビジネス契約書をベースに審議する。
注意事項は以下の通り。
①タイトルに間違った内容は記載しない。
②契約書、合意書、覚書、協定等どれであっても効力に差は無い。
③契約締結日は決して、バックデイトはしない。仕方ない場合は、契約の効力に関する遡及条項で対応するのが良い。
④印鑑は、実印が有効。認印の場合は、本人が押印したことの証明が必要になる。押印はあくまでも、本人の意思によりなされたことが重要である。
⑤電子署名についても、押印と同等の効果を認めている。
契約書本文には、必要な条項を盛り込む必要がある。記載されていない部分は、民法が適用される。
相手側が自社の商品やサービスに一番魅力を感じ、最も期待が高まっている取引開始時に、契約内容は整理をしておくべき。
契約書の内容の分類は以下の通り。
| ①取引事項に関する条項 | ・目的物 ・価格 ・仕様 ・納入、納入時期 ・支払時期、支払い方法 ・所有権の移転時期 など |
| ②取引上の問題に対応するための条項 | ・契約不適合責任 ・損害賠償責任 ・危険負担 ・期限の利益の喪失 ・契約の解除 ・相殺 など |
| ③契約に付随する条項 | ・秘密保持条項 ・裁判管轄条項 ・自動更新条項 ・誠実協議事項 など |
契約書には13種類の契約があるが、以下の通り。
⑴財産の移転を伴う契約(何について、いつ、どこで履行するのか、対価をどうするのか)
① 無償→贈与
② 有償→売買
③物と物→交換
⑵財産を一定期間貸す契約(何を、いつからいつまでなのか、返還時期、利息をそうするのか)
①無償→使用貸借
②有償→賃貸借
③同種のものを返還→消費賃借
⑶労力を提供する契約(契約の目的は何か、何についての契約か、いつからいつまでか、対価はどうするのか)
①指揮命令下の労務の提供→雇用
②一定の仕事の完成→請負
③一定の事務の提供→委任
④物の預かり→寄託
⑷その他
①組合
②終身定期金
③和解
上記の13種類のうち、ビジネス契約でよく使うのが、「売買」「賃貸借」「消費賃借」「請負」「委任」である。
契約内容は、記載が無いと民法が適応されるが、民法の規定とどう違うのか認識し、相手側と協議する必要がある。そのまま契約しているものが多いが、とても危険。契約の協議があるのがあたりまえ。
取引条件などは、5W1Hで、しっかり考えないといけない。
その他の注意事項の概要は以下の通り。(基本は、民法との変更のポイントを理解しておくこと)
全ては記載できないので、参照し、しっかりと規定すること。
相手側は、契約知識を試しているケースもあるので、協議するのが当たり前だと思わないと不利な契約となる。
●価格
・明確に明記すべき。
・消費税の記載も明記すべき。
・再販売価格の指定は、独占禁止法違反になる可能性があるため、あくまで参考価格にとどめる。
・委任契約では、合意がない限りは報酬が生じないと規定されている。
●目的物の引き渡し
・実際の取引に応じた規定にするのが一般的です。
・(納品)代金と同時化、先に納入か。
●代金・報酬の支払時期
・実態にあった条件を定めておくべき。
・民法は、契約の種別にもよるが、引き渡しと代金・報酬は同時が原則。(請負は完成後)
・いつ締めのいつ払いにするのか明記することが基本。
・支払日が土休日になった場合の処置も記載が必要。
・下請法が対象の場合、繊維関係で90日、それ以外の分野では120日までのサイトにする。
・振込手数料の負担の明記も必要。
・銀行振り込みを指定することにより、事実上、手形取引を防止することができる。
●知的財産権の帰属
・知的財産権は多岐に渡っており、二次著作物に関する権利の帰属も必要によっては、明記すべき。
・翻訳権や二次著作物に関する権利も委託者に帰属させたい場合には、契約に明記が必要
・著作者人格権への配慮が必要
・特許を受ける権利及び特許権について権利の譲渡や実施権の許諾など処理が必要
●再委託
・相手側に勝手に再委託されれば困るケースもある。
・「再委託する場合は、あらかじめ許諾が必要」など、再委託の禁止や制限の条項を置くべき
●継続的な取引の場合の取り決め
・基本契約時に、個別の取引に想像を巡らせてチェックしなければならない。
●契約不適合責任
・民法では売買契約時、追加請求権がある。原則として買主が追完方法を選択できるが、売主が選択する追完方法が買主に不相当な負担をかけるものでなければ、売主が選択できる。
・契約内容の不適合が、買主の帰責事由によるものである場合、買主は追完請求できません。
●代金減額請求権(以下は例です)
・買主は催告するこ以下は例ですに代金の減額を請求することができる、との規定もある。
・行使期間は、1年以内に買主からの通知が必要。消滅時期は、債権者が権利を行使できることを知った日から5年以内。時効は権利を行使できる時から10年間。
●知的財産権に関する保証条項
●損害賠償条項
●危険負担
●相殺条項
●契約解除(消費者契約と解除、委任契約と解除)
●権限の利益喪失条項
●連帯保証人
●秘密保持
●合意管轄の条項
●有効期間
あくまでも、注意事項の抜粋なので、詳細は弁護士さんへご相談することをお勧めします。
minne


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=18407803&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9927%2F9784806529927.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)