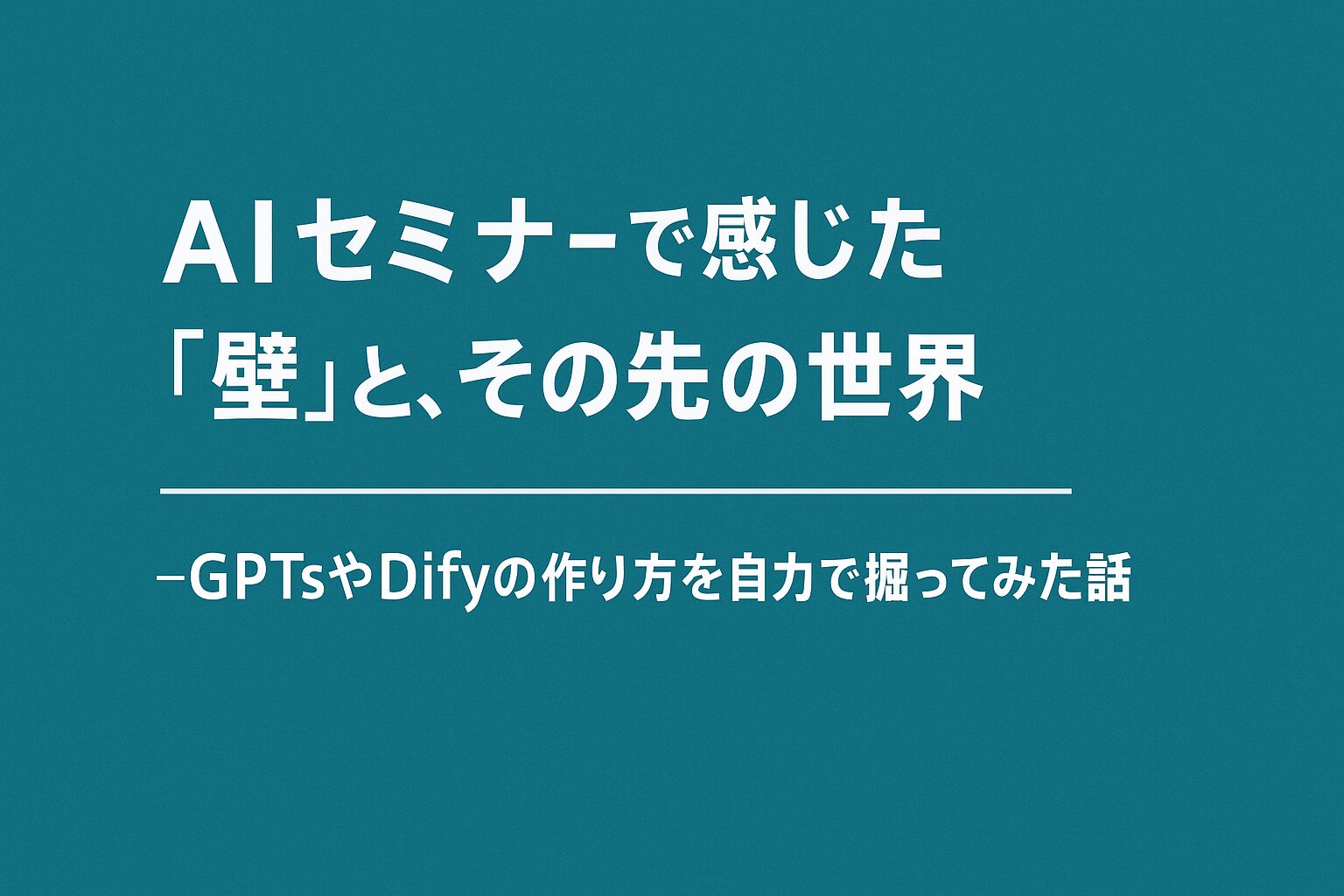日本の農業は大規模化すべきか?—農家よりJA職員が多い現状を問う
カテゴリ
- 農業政策
- 組織改革
- 地域経済
はじめに:現状認識と問題提起
昨日は大前建一先生のお話を聞いた。日本の農業は、衰退と政策の変遷の流れの中で今、大きな岐路に立たされています。その中でも、JA(農業協同組合)は絶対的な存在感を持ちながらも、組織人員構成に大きなアンバランスが存在します。特に、「農家よりもJA職員が多い」という構造は、農業現場にそぐわない支援体制や組織としての非効率性を招いています。本記事では、現状の実態から問題課題を分析し、大規模化・再編への道筋を検討します。
1. JAと農家、組織規模の比較
組合員と職員の規模
農林水産省によれば、令和4年度現在、JAの「正組合員」(主に農家)は約393万人。さらに准組合員(非農家会員)が634万人にのぼり、計約1,027万人と高水準です農林水産省+2JAグループ+2厚生労働省+2。
一方、職員数は約171,917人で、過去10年で4.3%減少しましたが、それでも数十万人単位です農林水産省+1ja-agri.jp+1。
この数字からわかるのは、「正組合員1人当たりJA職員0.043人(約4.3人に1人)」。さらには准組合員も支える必要があるため、実質的な負担率はより高いとみられます。
農家人口の減少と職員比率
1960年代から農家(基幹的農業従事者)の数は4分の1近くに減少していますダイヤモンドオンライン+5note+5JAグループ+5。農家人口の減少にも関わらず、JAの職員比率は一向に軽くなりません。
むしろ、大規模な金融業務や共済業務の領域では職員数を維持もしくは増加させており、付随的に農業支援関連の職員数も大きく減っていないといった逆説的な状況にあります。
2. なぜJA職員が多すぎるのか
① 非農業領域の肥大化
JAは信用事業(金融)と共済(保険)ではメガバンクと比肩する規模にまで成長しています。農業支援よりも金融・保険業務の収益構造に依存しており、そのための人員が必要とされているのが現実ですnote+1農林水産省+1。
② 准組合員の増加に伴う対応要員
農家以外の会員が全体の過半数を超える背景には、地域コミュニティ機能や生活サービス提供への要望があります。その対応には、農業とは異なるスキルが必要となり、職員数の維持・増加につながっていますnote+1agridtc.or.jp+1。
③ 営農指導員確保と難航
一方で、農業技術・経営指導を担う「営農指導員」は令和3年度で約16,000人程度ですJAグループ+1厚生労働省+1。農家数に比すれば極めて少なく、農業現場への直接支援は限られている矛盾があります。
④ ノルマ圧力による離職
金融・共済では販売ノルマが問題視され、職員離職の一因となっています。特に若手職員からの不満が多く、組織の硬直化を招いています。
3. 大規模化すべき本質的理由
効率化と集中人員配分
農業の担い手は少数化が進む一方、JAの支援能力が農家数に見合っていない現状では、無駄な組織維持にエネルギーを割いています。農業支援に必要なリソースを集中させるためには、大規模化・再編が不可欠です。
国内外の競争環境の変化
食料供給網がグローバル化する中、日本農業はスケールメリットを持つ必要があります。大規模化によって、機械化、ICT化、人材育成の加速が期待できます。
組織としての役割再定義
JAの金融・共済業務も重要ですが、農家を支え地域農業に寄与する本来の役割にリソースを振り向けるには、農業支援組織としての在り方を再定義する必要があります。
4. 大規模化・再編の課題
地域の自主性との矛盾
地方に根ざした小規模JAは地域の実情や文化をよく理解しています。大規模化によって、それらの現場知が失われる三次的リスクがあります。
職員の再配置と雇用問題
金融・共済領域での職員余剰が生じれば、人員整理・再配置が不可避です。地域雇用への影響も考慮すべき課題になります。
法制度の制約
JAは特定の法律のもとに構成されています。合併や事業分離には法的手続きと政治的調整が求められ、容易ではありません。
5. 解決に向けた提案
ステップ1:組織・人員の透明化
どこに人員がどれだけ配置され、成果や役割はどうかを見える化する。
ステップ2:営農指導部門への再投資
農家数に応じた適正な営農指導員数を確保。デジタル・機械化支援体制の強化。
ステップ3:業務分離・専門化
金融・保険業務と農業支援業務を法人的に分離し、それぞれ最適経営を回す。
ステップ4:地域合併とスケールメリット活用
複数JAの統合により、効率管理・人員共有・資材調達を合理化。
ステップ5:法制度改正と支援施策
MAFF・官邸とも連携し、JA法や農協制度改革に向けた政策提言を行う。
おわりに:本質は「農家支援の再定義」
JAはこれまで、地域農業とともに歩んできました。しかし、現状は従来の延長線上での組織維持が優先され、農家支援の本質が見えづらくなっています。農家より多い職員数という現実は、むしろ「転換のチャンス」を示唆しています。
大規模化とは単に規模を大きくする話ではなく、「どう効率的に、農家を支えるか」という本質への問いです。日本農業の将来を見据え、今こそJAは農家と未来のために再定義されるべき存在と言えるでしょう。


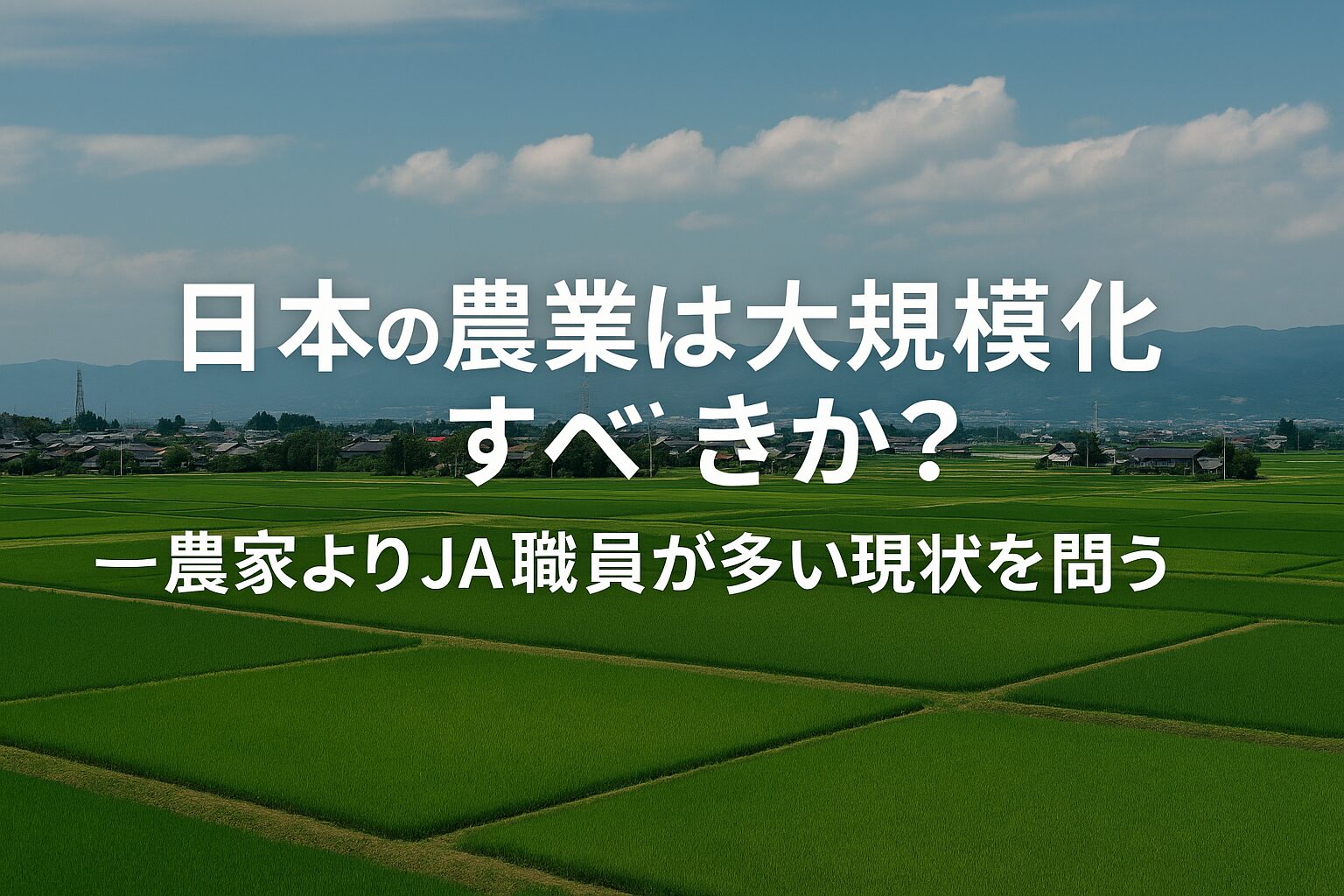
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2a140235.35cca56c.2a140236.ee5bd091/?me_id=1278256&item_id=14912649&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F5157%2F2000003575157.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)