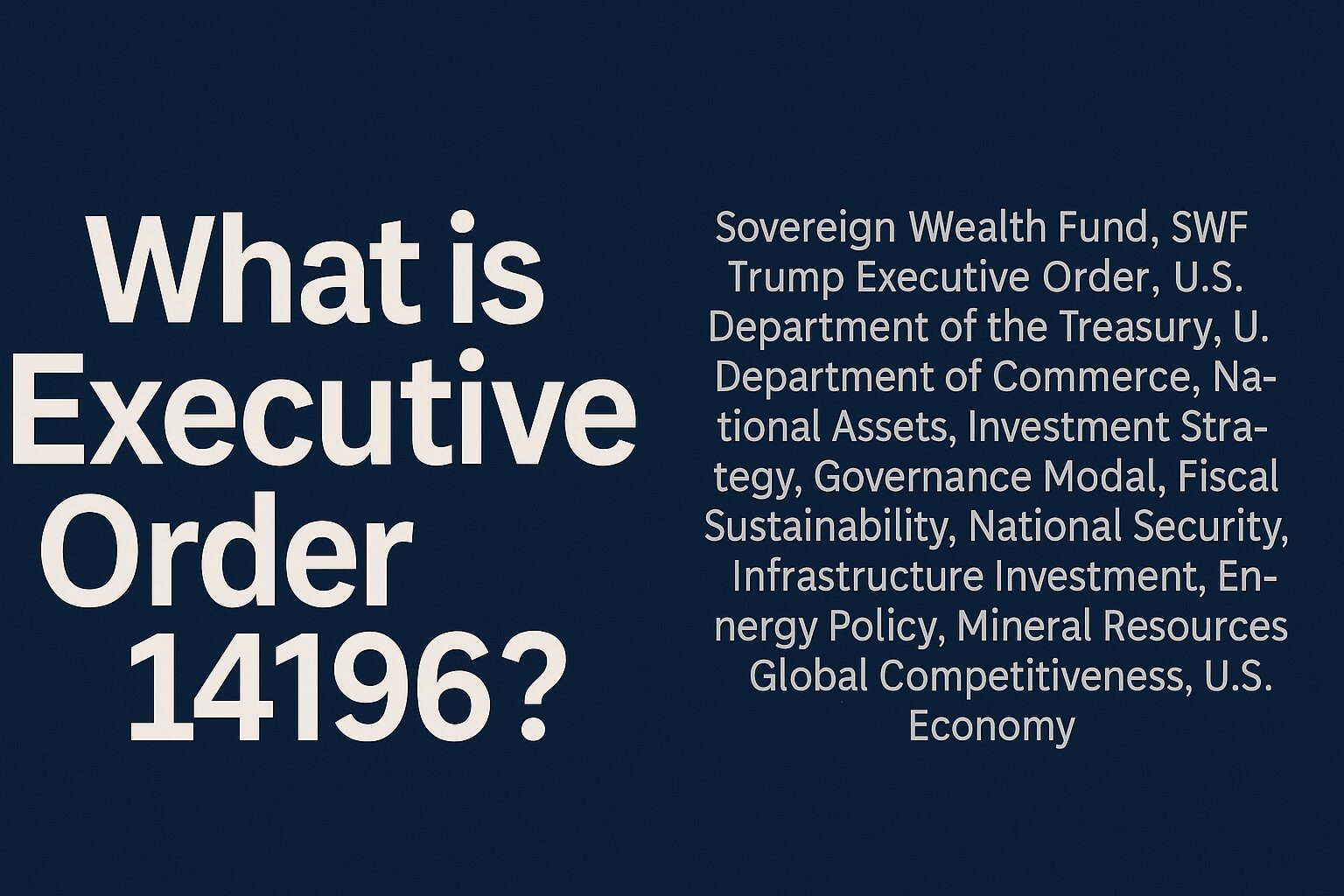🇨🇳富の「大移動」と日本の未来:相互主義、相続税、そして私たちが抱く違和感の正体
序章:MBA教室で感じた「時代の転換点」
先日、国内の社会人大学院MBAの教室で感じた異変は、私にとって大きな衝撃でした。クラスの正規学生のほとんどが、中国からの留学生だったのです。彼らが集まる背景には、本国で崩壊の危機にある不動産市場と、対照的に魅力的な**日本の「永続所有権」**があります。
しかし、この現象は単なる経済ニュースでは終わりません。彼らは日本の不動産を自由に買える一方で、私たちは中国の土地を取得できません。この非対称な状況、つまり**「相互主義の欠如」と、日本の「相続税制の矛盾」**が絡み合い、この国の富のあり方を根本から変えようとしているのです。
💥 第1章:中国の「使用権」崩壊と日本の「所有権」という名の逃避先
中国不動産は「定期借地権」の変形
中国では、土地の所有権は国にあり、個人が購入するのは最長70年の**「土地使用権」**です。バブルの崩壊は、この「使用権」の価値を暴落させました。
一方で、日本の不動産は永続的な**「所有権」(Fee Simple)が認められており、これはまさしく「永遠に続く富の保証」**です。本国で資産の安定性に不安を覚える富裕層にとって、日本の不動産は「安全資産」としてこれ以上ない魅力的な逃避先に見えます。円安も相まって、この流れは加速する一方です。
私たちが抱く「違和感」の正体は「相互主義の欠如」
私たちは、特定の国の人々に対して嫌な感情を持っているわけではありません。しかし、相手国では自国民の土地取得が厳しく制限されているのに、日本では野放しにされているという事実に、違和感を覚えます。
これは感情論ではなく、国際的な**「相互主義」の観点からくる当然の疑問です。大正時代に制定された外国人土地法は相互主義の制限を可能としましたが、国際的な自由主義経済の原則から、これまで一度も発動されていません。このままでは、「富の流入」が短期的利益をもたらす一方で、長期的に日本の安全保障上の懸念**や、日本人による住宅取得の困難さという副作用を生む可能性が高いのです。
💸 第2章:富裕層の「最後の壁」—日本の相続税の矛盾
さて、彼らが日本の不動産を買い進めたとして、次に直面するのが日本が誇る高い**「相続税」**です。この税制にも、国際化時代に無視できない大きな矛盾があります。
矛盾1:富の再分配か、事業承継のペナルティか
日本の相続税の最高税率55%は世界でも有数です。その根拠は「富の再分配」とされています。しかし、この税制が中小企業の事業承継を阻害しているという批判は根強い。
- 企業価値の多くを占める非上場株は簡単に売れず、納税のために事業をたたむか、切り売りする事態は、日本の活力や雇用を奪う「ペナルティ」でしかありません。
- 本当に富を再分配したいなら、一部に高税率をかけるだけでなく、課税ベースを広げ、税率を浅く広くする方が、社会全体の公平性に資するのではないでしょうか。
矛盾2:日本人には厳しい「10年ルール」、外国人には?
さらに、日本の相続税は**「全世界課税」が原則です。富裕層の海外への「税逃れ」を防ぐため、日本国籍を持つ限り、家族全員で海外に移住しても、相続発生前10年間は国外財産に課税される「10年ルール」**という厳しい呪縛があります。
しかし、海外の富裕層が日本国内の不動産を取得した場合、その資産は日本の相続税の課税対象になりますが、彼らが一定の要件を満たす非居住者であれば、**国外の資産(本国の資産)**には日本の相続税はかかりません。
つまり、日本人が海外に資産を移して相続税から逃れるのは困難ですが、外国人富裕層は**「日本国内の不動産」という魅力的なストックを所有しながら、「本国の資産」**は日本の相続税の網から守る、という戦略が可能になるわけです。
結論:私たちが選ぶべき「富のマネジメント」の道
富の移動は止まりません。私たちが議論すべきは、排他的な感情ではなく、この流れをいかに国益に資する形にマネジメントするか、です。
- 「相互主義」の再考:国際協定の壁があるとはいえ、安全保障や国境離島の規制を強化したように、「相互主義」を外交的な交渉材料として、**「土地」**という国民の根幹的な資産に対する公平性を主張し続けるべきではないでしょうか。
- 「相続税制」の改革:事業承継を円滑にし、富の再分配と経済の活性化を両立できる、国際競争力のある税制へと舵を切る必要があります。
あなたの疑問は、単なる違和感ではなく、**「日本のルールで、日本の富を、誰がどう守るのか」**という、国家の根幹に関わる問いです。



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=21458216&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4243%2F9784492224243_1_47.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)