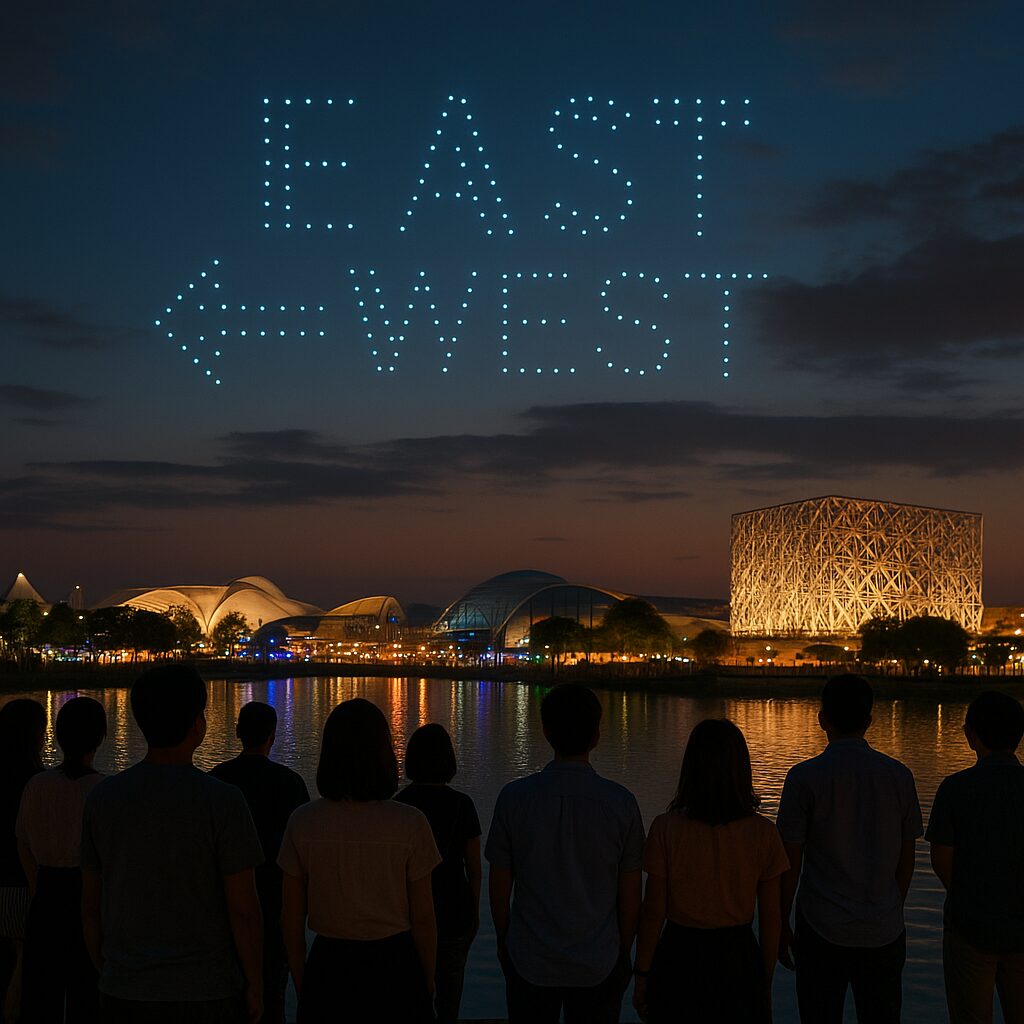「本を書きたい」衝動を形にする——ヒューマン・アセスメントと会社の手仕舞いに挑む50代起業家の視点
はじめに:なぜ今「本」を書くのか?
50代で起業してから数年、自分の経験を「言葉」に残したいと思うようになった。それは単なる記録ではない。これからの世代にバトンを渡すように、人生の節目をどう切り抜けてきたか、そしてどう終えるべきかを、自分の言葉で綴っておきたいと思ったからだ。
書きたい本は2冊。(あとで小説も書き残したい)
- 「ヒューマン・アセスメント」:人材育成に長く携わってきた経験を土台に、人の可能性を見抜き、引き出す方法を書き残したい。
- 「会社の手仕舞い方」:50代で起業し、自分の会社の未来を見据える今だからこそ、経営の始まりと終わりを自分ごととして記しておきたい。
第1章:「ヒューマン・アセスメント」は、なぜ今必要なのか
かつての人材評価は、学歴や職歴、成果主義に偏りすぎていた。しかし、VUCA(不安定・不確実・複雑・曖昧)な時代において、それだけでは人の価値を測れない。
「ヒューマン・アセスメント」は、以下の3点を重視する考え方だ。
- ポテンシャル:今できることより、将来できそうなこと
- 行動特性:どういう場面でどんな反応をするか
- コンピテンシー:成果を出すための思考と行動のパターン
部下や若手が成長する瞬間を何度も目にしてきた私にとって、この考え方は机上の空論ではない。「人を見る目」は経験によって養われるが、再現性を持って伝えることができると信じている。
第2章:会社は「終わらせ方」が9割
日本では、「起業」のノウハウは溢れているが、「会社の終わらせ方」に関する情報は少ない。特に個人事業や小規模法人を立ち上げた50代以上の経営者にとって、事業継続と同じくらい重要なのが「事業の畳み方」だ。
- 廃業届の出し方
- 法人解散の手続き
- 従業員・取引先との円満な関係整理
- 残った在庫や資産の処理
- 税務上の注意点
…どれも避けて通れない。しかし、実務と感情が複雑に絡むため、心理的な負担も大きい。
「終わり方」を知っている経営者は、逆に強い。未来に向かって、いつでも「次の一歩」を選べるからだ。
第3章:50代で起業するということ
「もう年だから」と言う人がいるが、50代での起業はむしろ「円熟のスタート」だ。社会経験、人脈、信頼、そして失敗を恐れない胆力。すべてが武器になる。
しかし、同時に現実的な選択も求められる。
- 家族への説明
- 資金繰りの見通し
- 自分の健康
- 事業継続の出口戦略
私自身、起業してから「孤独」と「自由」が常に同居していた。それでも、「自分で決められる生き方」に手応えを感じている。
第4章:「本を書く」ことは、人生を棚卸しする行為
ブログやSNSではなく、**「本」**として残す意味は何か?
- 情報を体系化することで、自分の思考が深まる
- 誰かに読まれる前提で書くことで、文章に責任が生まれる
- 過去と未来を見つめ直し、自分の「原点」に気づける
「ヒューマン・アセスメント」も「会社の手仕舞い」も、自分だけのテーマではない。多くの人にとって、これからの人生に関わる普遍的な問いなのだ。
第5章:書くために、始めた5つの習慣
- 毎朝15分だけ、自分に手紙を書く
- 読み返しても恥ずかしくない言葉で書く
- 誰か1人を思い浮かべて書く
- フィードバックを受け取る勇気を持つ
- 出版のハードルを下げる(最初は電子書籍でもOK)
本を書くのに「正解」はないが、継続する仕組みを自分で作ることはできる。
おわりに:「書きたい」は「生きたい」の裏返し
本を書くという行為は、「誰かに伝えたい」という想いの現れだ。そしてそれは、**「もっと生きたい」「まだ伝えきれていないことがある」**という、生の衝動でもある。
あなたも「書きたい」と思ったことがあるなら、もうその時点で一歩踏み出している。私と同じように、50代でも、60代でも、遅すぎることはない。


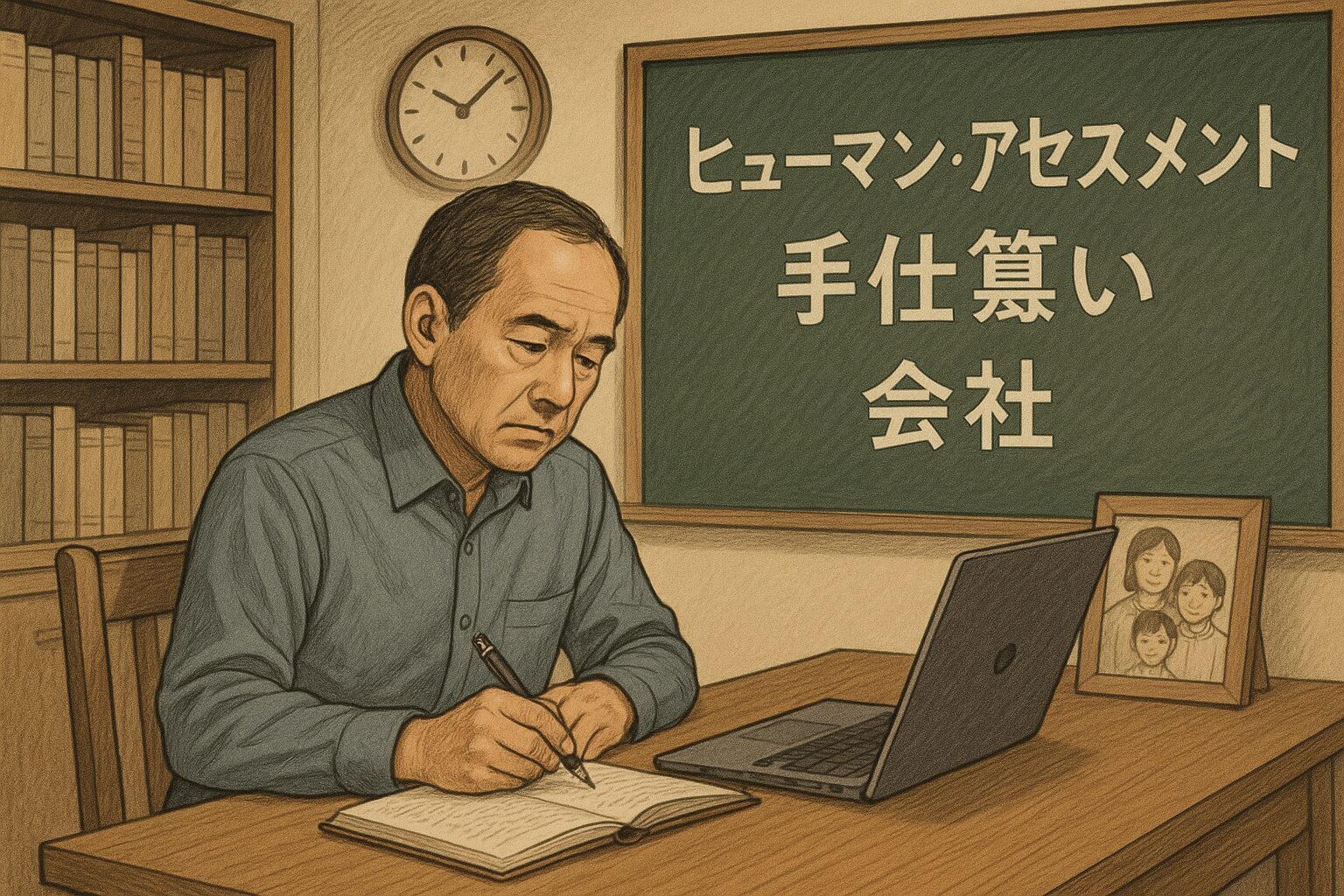
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=16832528&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9071%2F9784062189071.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)