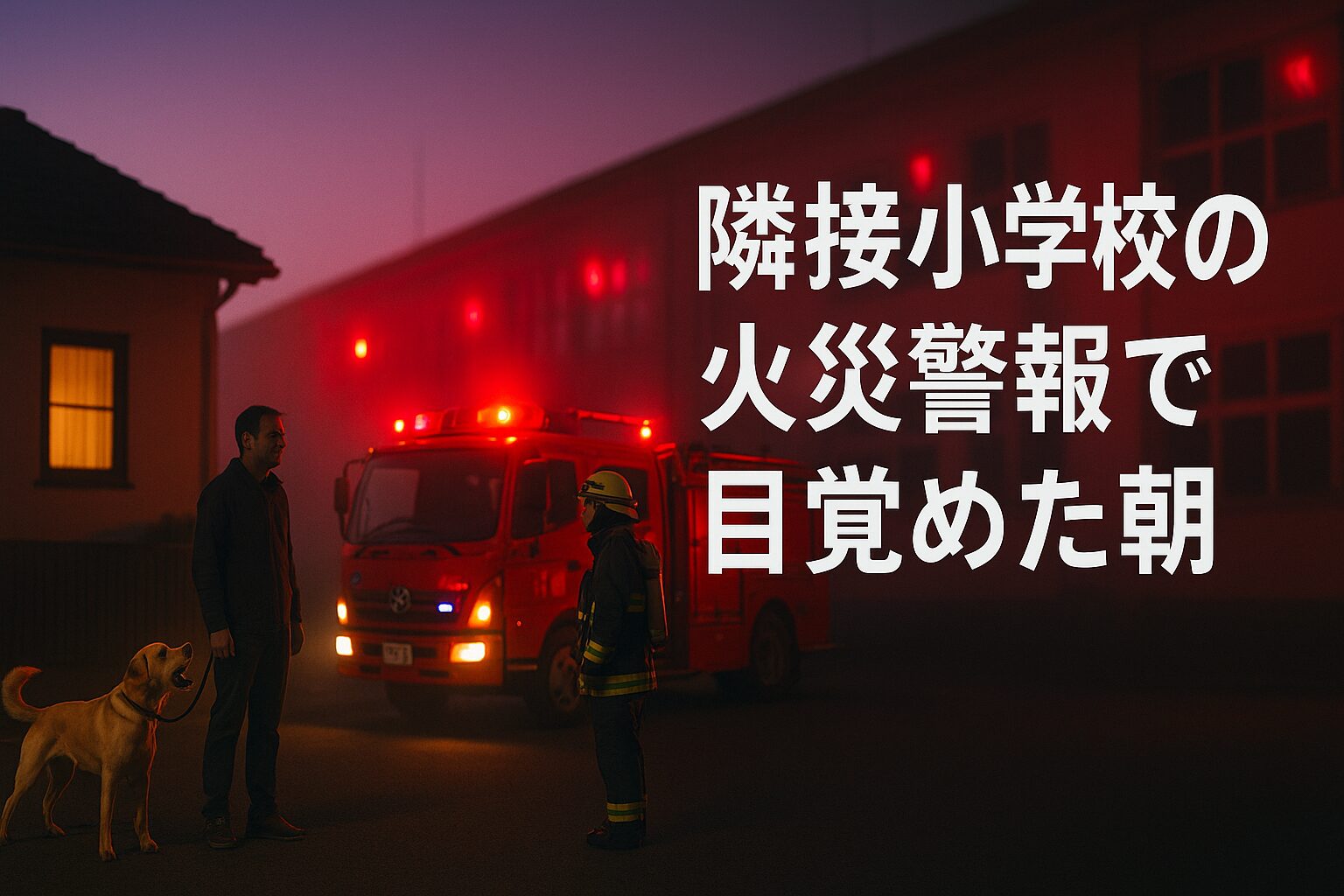お盆にAI学習が進まない理由と、スライド自動化を“編集前提”に作り直す戦略
※アイキャッチ画像はチャット欄に添付しています/本文末にキーワード・ハッシュタグあり
日付:2025-08-18
カテゴリ:AI活用/スライド作成/生産性向上/ワークフロー設計
- イントロ:お盆に“徹底学習”するはずが、思ったほど進まない
- いま詰まっている“本質的な”課題の棚卸し
- 目指す完成像(Definition of Done)
- 戦略A:スライドマスターで“字幕前提”の土台を作る
- 戦略B:AIは“内容のJSON”、描画はスクリプトで
- 戦略C:PPTXではなく“元データ”をGit管理する
- 戦略D:字幕ワークフローを最初から設計に入れる
- 戦略E:言葉+スライドが淡白に見える時の“抑揚コントロール”
- 戦略F:生成AIへの“プロンプト規約”
- ミニマクロ:既存スライドを“字幕対応”に一括補正
- 1日スプリント計画(お盆明けの実行案)
- 学びのログ(今回の気づき)
- まとめ:アウトプットが出れば、先行できる
イントロ:お盆に“徹底学習”するはずが、思ったほど進まない
お盆期間に「AIを徹底的に学習する」と決め、スライド自動作成ツールも一気に試してみた。ところが、進捗は思ったより伸びなかった。アウトラインだけならAIは驚くほど速い。GensparkやSkyworkのような生成系ツールで雛形はすぐできる。しかし本当に使いたいのは「その先」——つまりあとから編集できて、編集内容が履歴に残り、次回は自動化で再現できる状態だ。そこまで行こうとすると、急に難易度が跳ね上がる。
さらに、今回は字幕を下に入れる前提がある。だからスライドの主要要素を上に寄せ、文字も大きくしたい。ところが自動生成のレイアウトはしばしば“器”(余計なフレームや装飾)を勝手に配り、こちらの意図を上書きしてしまう。言葉とスライドだけだと淡白に見える一方で、過剰な装飾は運用の敵。**「編集前提の自動化」**に設計し直す必要がある。
いま詰まっている“本質的な”課題の棚卸し
- 編集耐性の不足:自動作成されたスライドが、編集を重ねるほど崩れやすい。
- 再現性の欠如:同じプロンプトでも版によって結果が揺れる。バージョン管理が効きづらい。
- 字幕前提のレイアウト不整合:下部に字幕帯を確保したいのに、オートレイアウトがスペースを食い潰す。
- フォントとサイズの一貫性:スライドごとに文字サイズがばらつき、最終出力で読みづらい。
- 装飾の暴走:フレーム、飾り罫、影、グラデーションなど“器”が勝手に増殖し、情報伝達の邪魔になる。
- 履歴と差分の見える化不足:PPTXはバイナリで差分比較がしにくい。何を変えたか説明しづらい。
目指す完成像(Definition of Done)
- **JSON/Markdownの“元データ”**から、スライドが再生成できる。
- **字幕帯(Safe Area)**が常に確保され、主要要素は上方に揃う。
- フォント・余白・グリッドがテンプレートで固定される。
- 編集内容はGitで追跡できる(PPTXそのものではなく元データを管理)。
- AIは**「内容(言葉)と配置の指示」**を返し、装飾は最小限。
戦略A:スライドマスターで“字幕前提”の土台を作る
手順(PowerPoint)
- 表示 > スライドマスターを開く。
- 最上位マスターにガイドを引く:下端から10〜12%を字幕帯として薄いグレーの長方形でマーキング(印刷しないならプレースホルダーではなく図形でもOK)。
- タイトルと本文プレースホルダーを上方に移動し、字幕帯と重ならないよう高さを固定。
- フォントスタイル規約を設定:
- タイトル:日本語/英数ともに太め、48pt以上。
- 本文:28〜32pt、行間1.15〜1.3。
- 箇条書きは最大5行・1行8〜12語を上限。
- 配色トークン(Brand Primary/Accent/Neutral)をテーマカラーに登録。影や外枠の既定はオフ。
- 上記を含んだ独自レイアウトを数種作成:
Title-Only(字幕帯あり)Title + Bullets(3行まで)Big NumberComparison 2/3Diagram (Full-Width Top)
- テンプレート名に
_CC(Closed Caption)などラベルを付け、字幕対応テンプレだと分かるようにする。
ポイント:字幕帯は“透明なルール”ではなく視覚化しておく。AIやスクリプトで図形座標を計算する際、y座標の範囲を上部に限定すれば、字幕スペース侵食を根本から防げる。
戦略B:AIは“内容のJSON”、描画はスクリプトで
生成AIにPPTXそのものを作らせるより、**構造化データ(JSON)**を出させ、描画はpythonやApps Scriptで行うと壊れにくい。
1) スライドJSONの最小仕様
{
"meta": {
"theme": "caption-ready",
"font": {"jp": "Noto Sans JP", "en": "Inter"}
},
"slides": [
{
"layout": "Title-Only",
"title": "お盆にAI学習が進まない理由",
"notes": "冒頭の共感。字幕帯あり。",
"visual": {"type": "none"}
},
{
"layout": "Title + Bullets",
"title": "痛点",
"bullets": [
"編集耐性が低い",
"再現性が揺れる",
"字幕帯が確保できない"
],
"notes": "各行8-12語以内"
}
]
}2) Python(python-pptx)での描画例(字幕帯を確保)
from pptx import Presentation
from pptx.util import Inches, Pt
from pptx.enum.text import PP_ALIGN
SAFE_BOTTOM_RATIO = 0.12 # スライド下12%を字幕帯として確保
SLIDE_W, SLIDE_H = Inches(13.333), Inches(7.5) # 16:9
prs = Presentation('caption_ready_template.pptx') # スライドマスター済みのPPTX
# 例: Title-Only スライドを追加
slide_layout = prs.slide_layouts[0] # カスタム: Title-Only
slide = prs.slides.add_slide(slide_layout)
# 既定のタイトルプレースホルダーを取得
title_shape = slide.shapes.title
# 字幕帯を避けるように位置補正
safe_bottom = SLIDE_H * (1 - SAFE_BOTTOM_RATIO)
if title_shape.top + title_shape.height > safe_bottom:
title_shape.top = Inches(0.4)
title_shape.text = 'お盆にAI学習が進まない理由'
# 本文などを追加する際もsafe_bottomを上限として配置する
prs.save('output.pptx')3) Googleスライド派ならApps Script
- 元JSONをDriveに置き、Apps Scriptで読み込んでスライド生成。
- 下部に透明長方形を敷いてガイド化、テキストボックスのY座標最大値を
slideHeight * 0.88に制限。 - すべてセンチやピクセルではなく比率で管理すると、後のサイズ変更に強い。
戦略C:PPTXではなく“元データ”をGit管理する
- PPTXは成果物、JSON/Markdownはソースと割り切る。
/slides/src/*.jsonをGit管理、/slides/dist/*.pptxはビルド成果として毎回上書き。- 変更履歴は
CHANGELOG.mdに人間語で残す(例:「Slide #05: 箇条書き→図版に変更」)。 - 画像は
/assets/で管理。大きいファイルはGit LFSを検討。
差分の見える化
- JSON構造なら差分レビューが容易。レビューコメントを残せる。
- 自動CIでJSONからPPTXを生成し、毎回同じ見た目に着地させる。AIの“気分”への依存を下げる。
戦略D:字幕ワークフローを最初から設計に入れる
- ライブ字幕(登壇用):PowerPointの字幕機能や通訳アプリを使い、下寄せで表示。フォント・位置のカスタマイズは限定的なので、スライド側で領域を確保する発想が重要。
- 動画書き出し(配信用):
- スライドを動画化→
SRT/WebVTTを後乗せで焼き込み。 - 字幕は2行まで/1行32〜40文字程度、行間と余白を広く。下12%の帯からはみ出さない。
- スライドを動画化→
- 図版の配置原則:写真・図は上段にフル幅で。字幕帯と競合しないよう脚注は右上へ逃がす。
戦略E:言葉+スライドが淡白に見える時の“抑揚コントロール”
- Big Number:1枚に指標1つ。数字は200pt前後、説明は28〜32pt。
- Before→After:左に現状、右に理想。差分を単語3つで言い切る。
- 3カラム:課題/打ち手/効果。各カラム3行以内。
- ロードマップ:四半期ごとに1行、棒状タイムライン。アイコンは1枚1個まで。
- フレーム図:枠線は細く(1pt)、陰影はゼロ。“器”を増やさない。
戦略F:生成AIへの“プロンプト規約”
AIが勝手に器を配るのを止め、編集可能なJSONに限定するための雛形:
あなたはスライド脚本家です。出力は必ずJSONのみ。装飾・HTML・PPTXは生成しない。
制約:
- レイアウトは {"Title-Only","Title + Bullets","Big Number","Comparison"} のいずれか。
- 各スライドは 1 タイトル + 箇条書き最大5行(各行8-12語)。
- 字幕帯を下12%に確保する前提で、要素はその上に収まる内容だけを書く。
- “器”(フレーム、影、余計な図形)の指示は禁止。必要ならvisual.typeに"none"または"illustration"のみ指定。
出力例:
{
"meta": {"theme": "caption-ready"},
"slides": [
{"layout": "Title-Only", "title": "課題の整理", "notes": "冒頭の共感"},
{"layout": "Title + Bullets", "title": "痛点", "bullets": ["編集耐性が低い","再現性の揺れ","字幕帯の侵食"]}
]
}評価ルールも同時に書くと堅くなる:
- 各スライドの平均行長(語数)を計算し、8〜12語を外れたら修正。
- スライド数は10±2に収める。超過・不足時は自動で再編。
ミニマクロ:既存スライドを“字幕対応”に一括補正
PowerPoint VBA(例)
Sub CaptionReady()
Dim s As Slide, sh As Shape
Dim slideH As Single: slideH = ActivePresentation.PageSetup.SlideHeight
Dim safeBottom As Single: safeBottom = slideH * 0.88 ' 下12%は字幕帯
For Each s In ActivePresentation.Slides
For Each sh In s.Shapes
If sh.Type = msoTextBox Or sh.HasTextFrame Then
If sh.Top + sh.Height > safeBottom Then
sh.Top = 20 ' 上に押し上げる(px相当)
End If
If sh.TextFrame2.TextRange.Font.Size < 28 Then
sh.TextFrame2.TextRange.Font.Size = 28
End If
End If
Next sh
Next s
End Sub※細かい座標はテンプレ側で整備しておくと安定する。
1日スプリント計画(お盆明けの実行案)
Day 1:基礎整備
caption_ready_template.pptxを作る(マスター、配色、ガイド)。- JSONスキーマ最小版を決める(上記例でOK)。
Day 2:描画スクリプト
- python-pptxまたはApps Scriptで、Title/Bullets/BigNumberの3種を生成。
- Gitで
src/json→dist/pptxのビルドを自動化。
Day 3:プロンプト整備
- プロンプト規約と評価ルールを固定。
- 実サンプルを5本回して“器の暴走”が止まるまで調整。
Day 4:字幕導線
- 動画化とSRT焼き込みの手順書を作る。字幕の行長ガイドを反映。
Day 5:運用ドキュメント
- README/CHANGELOG/命名規則。新メンバーでも再現できる状態にする。
学びのログ(今回の気づき)
- 生成の速さより編集の耐性が価値。
- レイアウトは比率で考えると壊れない。
- 装飾は敵。器を増やさず、情報密度と抑揚で勝負。
- 字幕は仕様。あと付けではなく最初に領域を確保する。
- 成果物(PPTX)ではなく**ソース(JSON/MD)**を管理する。
まとめ:アウトプットが出れば、先行できる
お盆期間に理想通りの進捗が出なくても、今日の棚卸しでやるべき設計は見えた。次は「編集前提の自動化」を核に、テンプレ・JSON・描画スクリプト・字幕導線を一体化させる。アウトプットが出れば、それだけで先行できる。迷ったら装飾を捨て、要素を上方に寄せ、文字を大きく。“器”ではなく伝達そのものに集中しよう。


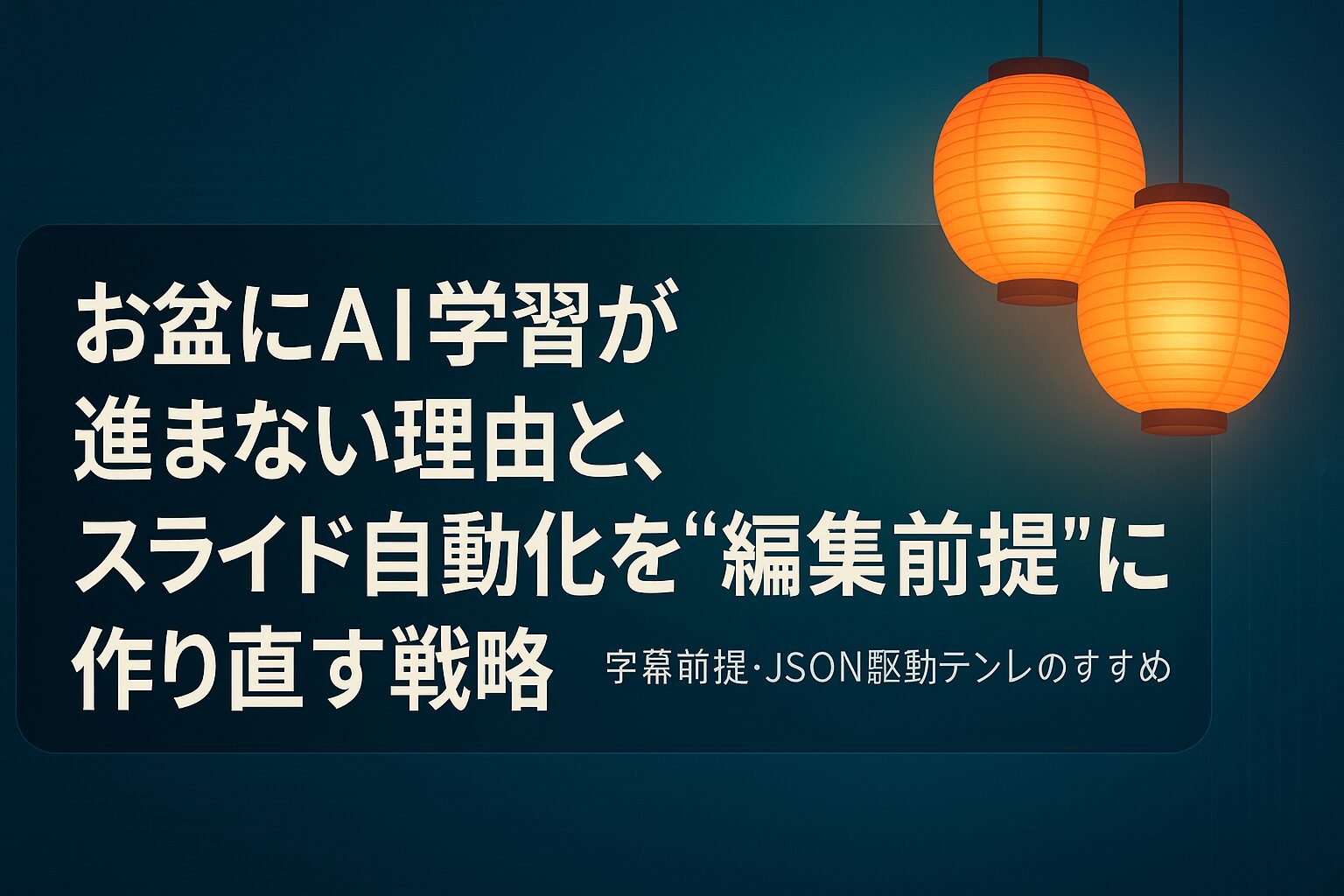
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=21550080&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2991%2F9784815632991_1_7.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)