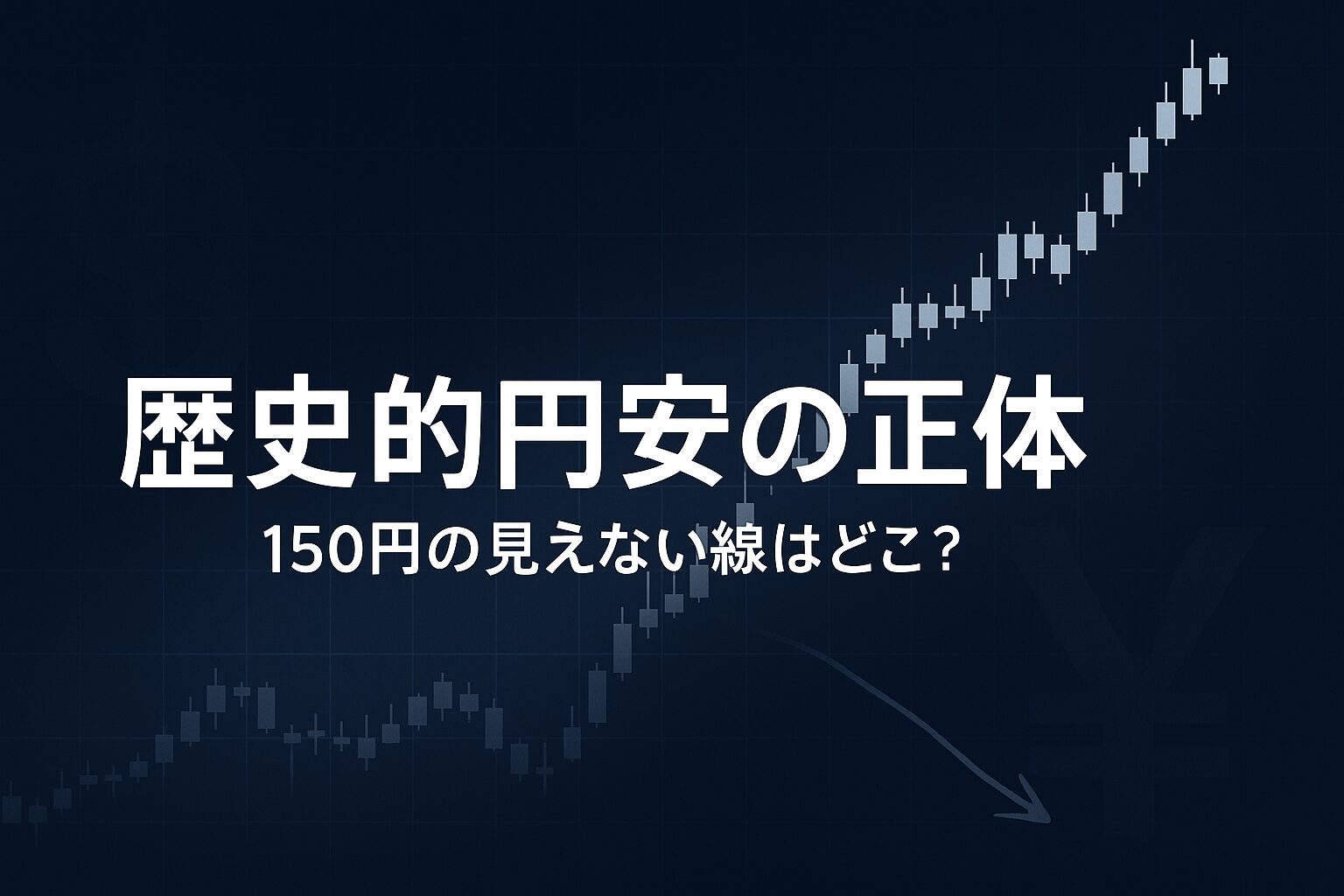1ドル152円の衝撃——円安が私の生活を侵食する。インフレ税という見えない刃
🏷️ カテゴリー
- 経済・マネー
- 日本社会
- ライフスタイル・生活防衛
- 個人投資・家計管理
📖 目次
- 円安1ドル=152円、静かに進む日本の通貨崩壊
- 株高という幻影——誰が得をして、誰が疲弊しているのか
- インフレ税の正体:政府が黙ってあなたの財布から奪う仕組み
- 「株をやめた後悔」から見える、個人投資家のジレンマ
- 私の小さな貯金が溶けていく日々
- それでも、私たちはどう生きるべきか——個人のサバイバル戦略
- 終章:通貨と心の価値を取り戻すために
✍️ 本文
1. 円安1ドル=152円、静かに進む日本の通貨崩壊
昨日、為替市場はまたひとつの節目を迎えた。
1ドル=152円——。
ニュース速報のテロップが流れた瞬間、私の胸に小さな不安が走った。
「また円安か。」
しかし、その“また”という言葉の裏には、
もはや驚きではなく、慣れと諦めが混じっている。
数年前、1ドル=110円台だったころを思い出す。
あの頃は、輸入品も手頃だった。
カフェのコーヒー豆も、ガジェットも、海外旅行も。
だが今、スーパーに行けば、
バターも、肉も、日用品も、静かに値上がりを続けている。
給料は上がらない。
それどころか、実質的には下がっている。
「物価上昇率−賃金上昇率」——これが、
今の日本人の“体感インフレ”だ。
2. 株高という幻影——誰が得をして、誰が疲弊しているのか
一方で、ニュースでは連日「日経平均が最高値更新」と騒がれる。
でもその数字は、私の生活を豊かにしてくれただろうか?
いや、していない。
円安による輸出企業の利益増加が株価を押し上げ、
海外投資家が円安を武器に日本株を買い漁っている。
だがその恩恵を受けているのは、ごく一部の投資家と大企業だ。
一般の人々の家計は、逆に圧迫されている。
ガソリン、光熱費、食費。
上がるものばかりで、下がるものがない。
「株をやめるんじゃなかった」
そう思うたびに、胸の奥がチクリと痛む。
あのとき、少しの恐怖で手放した株が、
今の円安で何倍にも膨らんでいる。
しかし同時に、その株高もまた“幻影”にすぎない。
円の価値が下がった分、数字が大きく見えているだけだ。
3. インフレ税の正体:政府が黙ってあなたの財布から奪う仕組み
インフレ税——。
それは、政府が直接「税金」として取るものではない。
しかし、**実質的には国民から資産を奪う“見えない税”**である。
インフレが進むと、お金の価値が下がる。
たとえば、100万円の貯金をしていても、
物価が10%上がれば、実質的な購買力は90万円になる。
誰にも徴収されていないのに、財布の中身は確実に削られていく。
そしてそれは、最も努力して貯金してきた人ほど痛い税だ。
節約して、コツコツ積み上げた人ほど、
静かに、その努力を奪われていく。
4. 「株をやめた後悔」から見える、個人投資家のジレンマ
「安全に現金で持っておこう」
そう思ったのは間違いではなかったはずだ。
だが、その“安全”の定義が変わってしまった。
かつては、現金=価値の保存だった。
しかし今や、現金=価値の減少だ。
銀行に預けたままの通帳を見て、
数字は変わらないのに、
買えるものが減っていく現実を知る。
それは、静かな恐怖だ。
5. 私の小さな貯金が溶けていく日々
日常の中で、それを最も実感するのはスーパーのレジだ。
以前は3,000円で買えた食材が、今は4,000円を超える。
外食も控え、電気をこまめに消す。
そんな小さな努力では、もう追いつかない。
貯金は減っていないのに、
生活は苦しくなっていく。
——これが、インフレ税の現実だ。
6. それでも、私たちはどう生きるべきか——個人のサバイバル戦略
では、どうすればいいのか。
悲観するだけでは、何も変わらない。
今できる現実的なサバイバルは、
「お金を守る」ことよりも「お金を動かす」ことだ。
- 円だけでなく、外貨資産・株・金などに分散する
- スキルを磨き、副収入の道を作る
- 固定費を見直し、生活の構造をスリム化する
- 自分の「時間価値」を意識して、浪費を避ける
これは単なる節約術ではない。
貨幣価値の変化に負けない生き方の構築だ。
7. 終章:通貨と心の価値を取り戻すために
1ドル=152円。
それは単なる数字ではない。
それは、「日本という国のあり方」が問われている数字だ。
そして同時に、私たち一人ひとりが
“どう生きるか”を突きつけられている数字でもある。
お金の価値が変わっても、
私たちの努力や思考の価値は変わらない。
——それを、忘れたくない。



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=21454826&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4783%2F9784166614783_1_15.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)