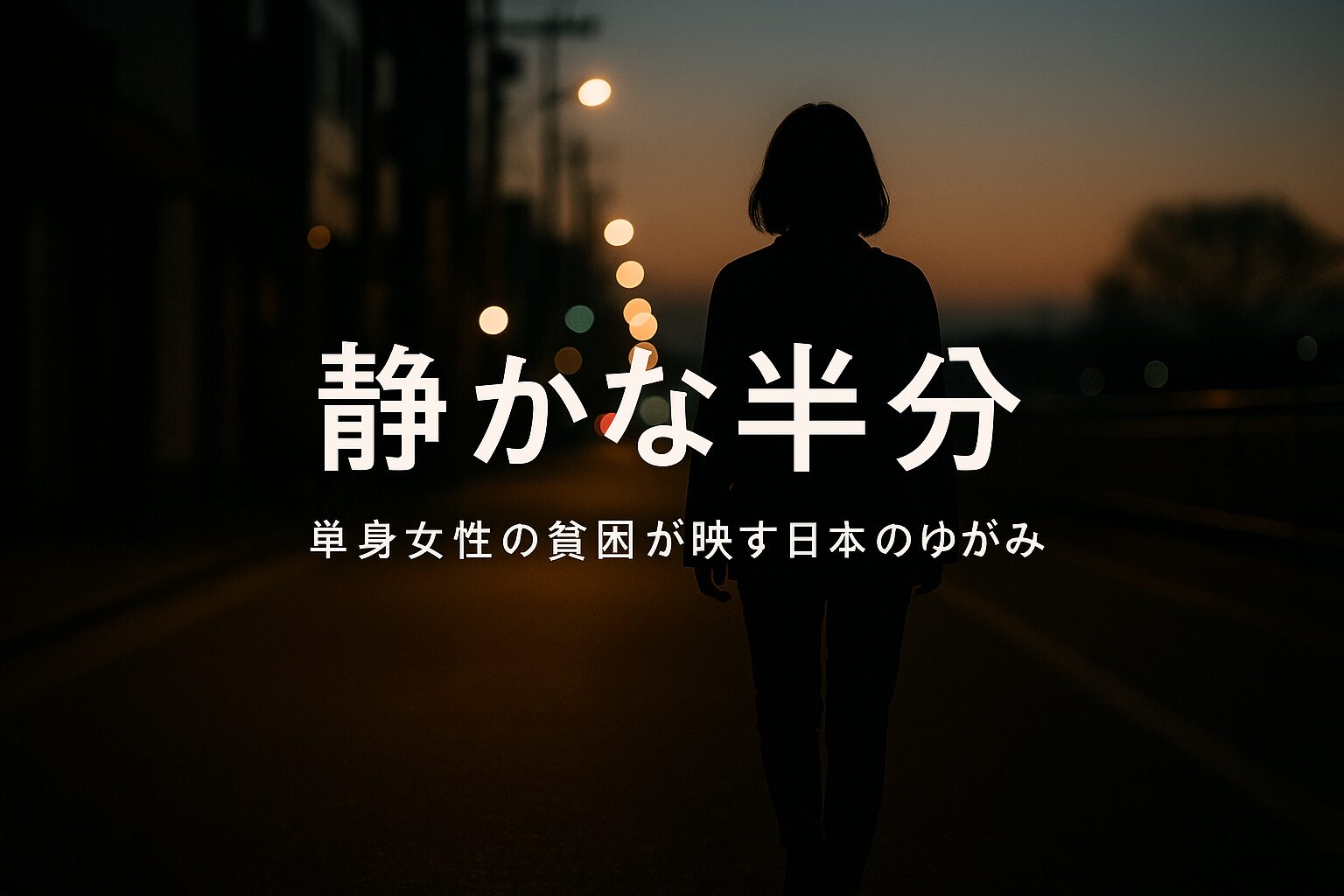🚗 日産の赤字の深刻さに思いを馳せて
〜2025年度上期決算を受けて:本社売却・固定費削減。それでも見えぬ出口〜
🏷 カテゴリー
ビジネス/経済分析/企業経営/自動車産業
目次
- 2025年度上期決算──「再び赤字」の現実
- 昨年度の“膿出し”から何が変わったか?
- 本社売却+固定費削減──象徴的だが十分か?
- ルノーグループとの関係整理──自主権の実態は?
- ブランド価値と「らしさ」の再構築課題
- 業界内の立ち位置:トヨタ・ホンダと何が違うのか?
- EV/電動化の遅れと世界市場での影響
- 希望の糸口はあるのか?次の一手を探る
- 結論:膿を出しただけでは足りない、“再成長”の思想改革が必要
1. 2025年度上期決算──「再び赤字」の現実
2025年度第1四半期~第2四半期累計(4〜9月)において、日産は売上高5兆5787億円と前年同期比-6.8%減、営業損益は-277億円の赤字、最終損益が-2219億円の赤字という厳しい着地となりました。株探+4Yahoo!ファイナンス+4マークラインズ+4
この数字が示すのは、単なる一時的な揺れではなく、構造的な課題が現時点でも顕在化しているということです。昨年度「膿を出した」とされていたはずですが、赤字という形でその後遺症が浮かび上がったと言えるでしょう。
特に、為替や米国の関税など外部環境の影響もあったとされ、「関税影響で1497億円の減益」であったと報じられています。TBS NEWS DIG
2. 昨年度の“膿出し”から何が変わったか?
日産は前年度、大規模な特別損益を計上し、過去の不採算事業やリストラ費用を一括処理しました。これが“膿を出した”という評価を生んだわけですが、今回の上期赤字によってその「膿出しが完了した」というストーリーに疑問符が付きました。
整理は進んだものの、以下のような“残りの課題”が浮かんでいます:
- 海外販売の落ち込み(特に中国・米国など主要市場)
- 電動化・EV戦略での遅れ感
- 固定費構造が依然として重い(人件費・工場・設備)
- ブランド“魅力”の低下と差別化の弱さ
つまり、「膿を出して終わり」ではなく、そもそも「何を育てるか」がこれからのテーマであることをより明確にしておく必要があります。
3. 本社売却+固定費削減──象徴的だが十分か?
日産は本社ビルを売却しリースバック契約を行うなど、象徴的なコスト構造改革を実施しています。上期決算資料でも、「固定費削減で上期80 0億円以上、通年1500億円超を目指す」などの数値が掲げられています。Yahoo!ファイナンス+1
しかし「象徴的」な改革が実際の収益構造改善に直結しているかというと、疑問が残ります。建物を売却してキャッシュを得るのは確かに“見える改革”ですが、毎期の損益を黒字化するには、固定費削減以上に“収益を増やす戦略”が必要です。
また、売却による帳簿上の利益があっても、事業そのものの稼ぐ力が戻らなければ根本的な改善とは言えません。固定費削減は手段であって目的ではない――この視点を忘れてはいけません。
4. ルノーとの関係整理──自主権の実態は?
日産は、長らく ルノーグループの中で資本・技術面での関係を築いてきました。最近では資本持株比率やアライアンスの構造が見直され、「自主経営」の回復が語られています。
しかし、実際には次のような矛盾が残っています:
- 開発・EVプラットフォームの共有が続いており、完全な独立とは言えない
- ルノーや他の提携先との構造が未だ緊密であり、「自由度」がどれだけあるかが見えにくい
- 世界戦略・製造戦略において、ルノーとの協業は一方でリスクヘッジだが、他方で日産固有の戦略を縛る素材にもなりうる
つまり、「自主権の取り戻し」は言葉としては出てきているものの、その実効性・深度には疑問が付きます。ブランド・市場戦略・技術ロードマップの各領域で“日産自身の決断”がどれだけ行えるかが鍵です。
5. ブランド価値と「らしさ」の再構築課題
かつての日産は、「走りの技術」「チャレンジングなイメージ」「革新的モデル」で世に印象を残してきました。しかし現在、市場における“日産らしさ”は希薄化していると感じられます。
例えば、EV初号機の「リーフ」など先駆的モデルがありましたが、その後の展開で他社に追い抜かれた印象を持つ人も多いでしょう。電動化競争が激化する中で、「では日産は何を“最も得意とするのか”」という問いが、あらためて浮き彫りになっています。
ブランド価値を再構築するためには:
- 製品そのもの(車種・技術・デザイン)に明確な“差別化ポイント”を設ける
- 市場・地域ごとの戦略を明確にし、“グローバル+ローカル”のバランスを取る
- 顧客に対して「選ばれる理由」を語れるストーリーを持つ
これらが不可欠です。
6. 業界内の立ち位置:トヨタ・ホンダと何が違うのか?
日本の自動車メーカーでは、トヨタ自動車がグローバル展開と利益構造の強さで牽引し、本田技研工業(ホンダ)が技術・ブランド・北米展開で存在感を示しています。
一方で日産は、
- グローバル展開において「大手」ではあるが、利益率・ブランド力ともにトップには届いていない
- 差別化戦略(例えば技術・EV)において明確なリードを保てていない
- 中途半端なポジションに陥るリスクを抱えている
この“中途半端”な立ち位置が、決断を鈍らせ、改革を遅らせる原因にもなりかねません。日産が再び強みを発揮するには、「どこで勝つか」「何を捨てるか」の明確な選択が必要です。
7. EV/電動化の遅れと世界市場での影響
日産がかつてEV先駆者として紹介された時期がありましたが、その後の展開では他社の成長スピードに追いつけていないという指摘があります。
2025年度上期決算でも、販売台数1.48 百万台という実績が発表されています。Yahoo!ファイナンス しかし、電動化という観点では、環境規制・競争激化・技術革新という3つの外部プレッシャーに対して、戦略の先手を打てているか疑問です。
競争激化によって「ただEVを出せばいい」時代から、「マーケット/顧客/技術・価格で勝てるEV/電動車を出せるか」が問われています。日産がこの転換を遅らせると、市場で存在感を失うリスクが高まります。
8. 希望の糸口はあるのか?次の一手を探る
それでも、日産には希望の芽があります。例えば、固定費削減や工場統廃合、エンジニアリング効率改善など、内部改革の動きは目に見えています。Electrek+1
新モデル投入・グローバル戦略の見直し・マーケティング刷新など、次の一手をどう打つかが鍵です。
特に重要なのは:
- 「収益をどう回復させるか」という視点を明確にすること
- 社員・組織が誇りを持てるストーリーを明確にすること
- 顧客から見て「日産を選ぶ理由」が明快であること
これらを備えたうえで、改革のスピードと規模を拡大できれば、復活の道筋は見えてきます。
9. 結論:膿を出しただけでは足りない、“再成長”の思想改革が必要
今回の上期決算が示したのは、単なる整理整頓では収まらない、より深刻な構造課題の存在です。
膿を出すことは大切でした。しかし、次のステップは「何を育てるか」「何に賭けるか」です。
日産に必要なのは、
- 固定費削減という“後ろ向き”ではなく、
- 成長を生む“前向き”な戦略
です。
そして、経営陣だけでなく、組織・ブランド・技術・顧客の四者が“もう一度誇りを持てる日産”を取り戻すこと。これが、真の再建=再成長の第一歩だと私は考えます。


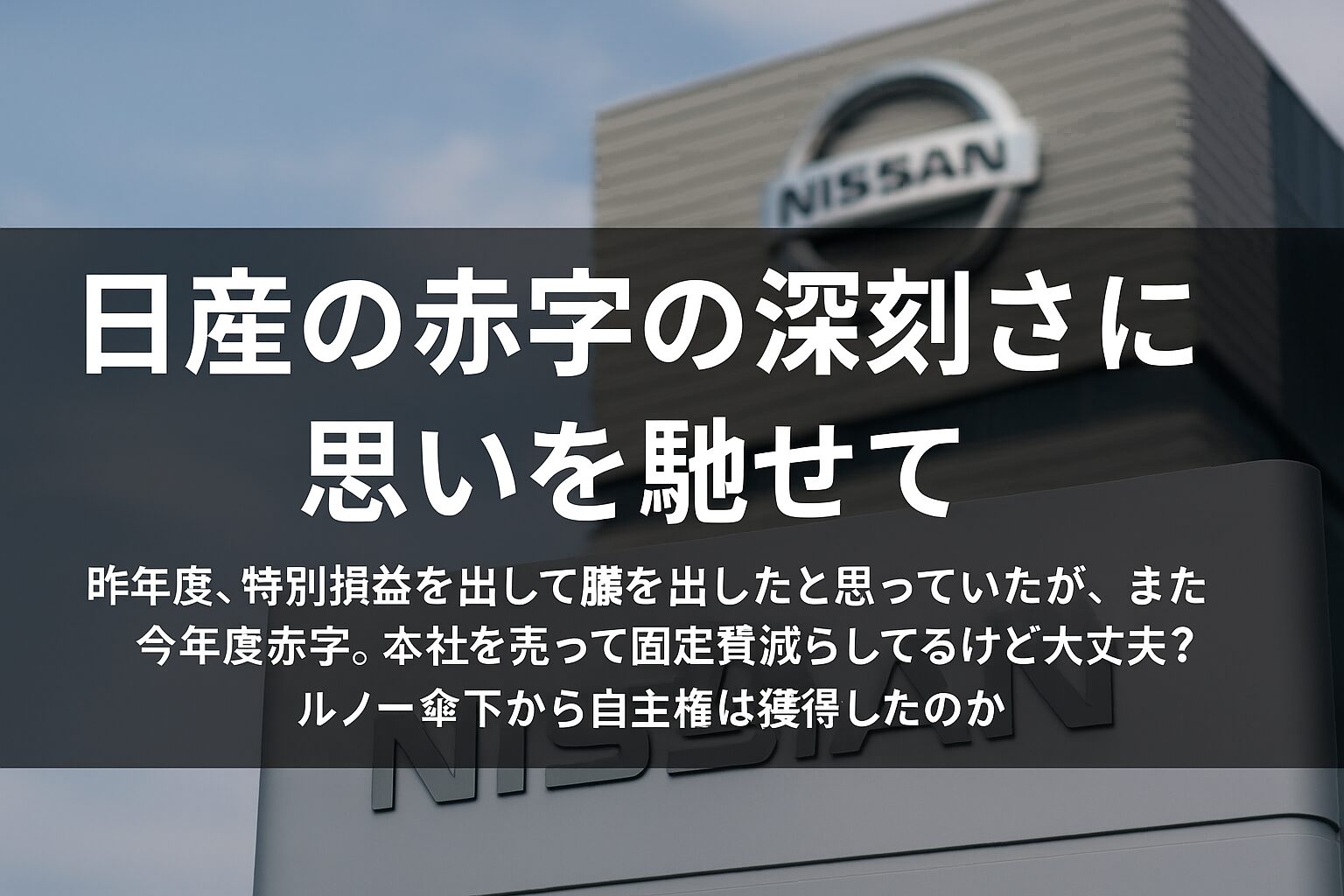
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=19502212&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1919%2F9784865811919.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)