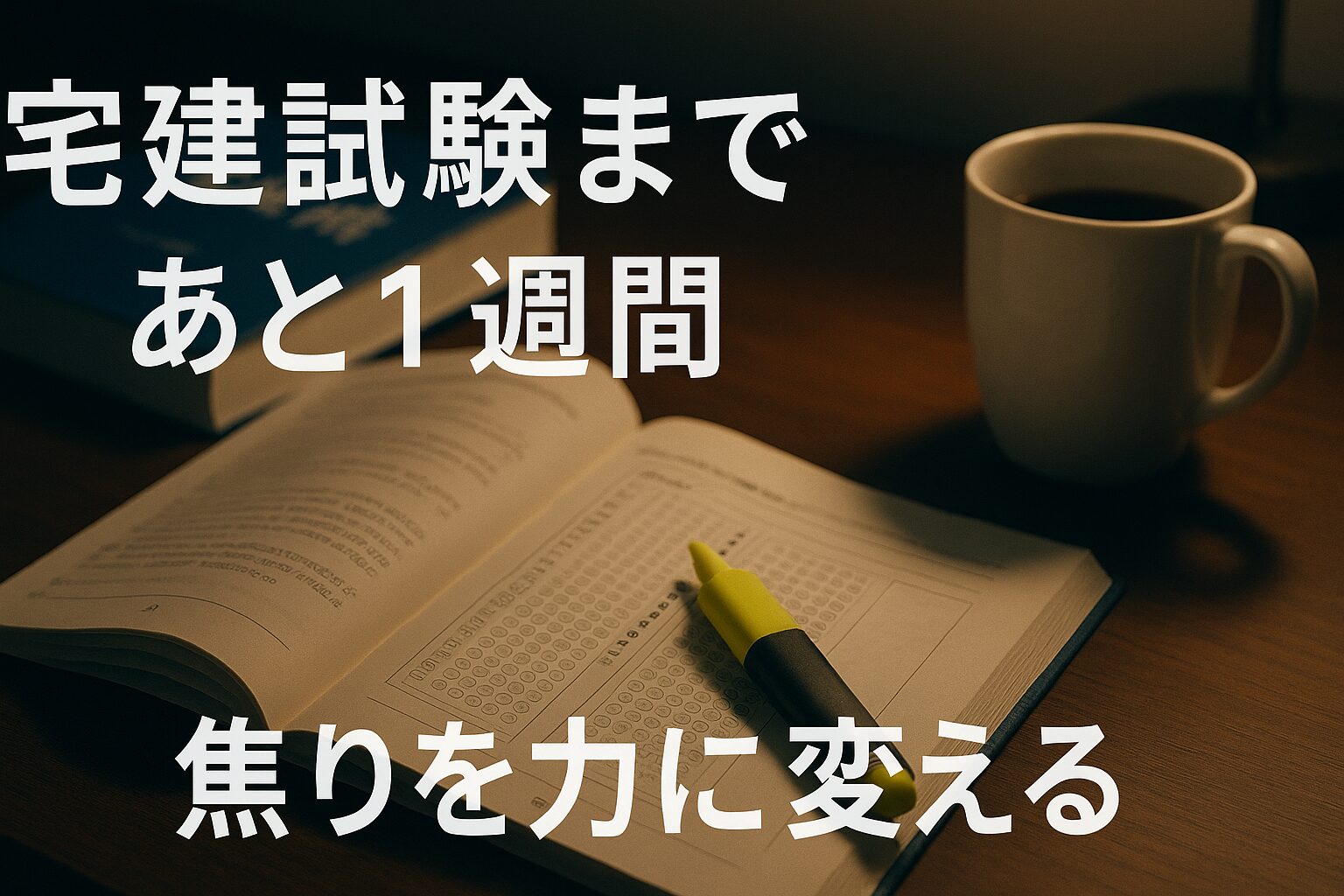明日は裁判——簡易裁判所へ向かう前夜、静かな不安と覚悟
🏷️ カテゴリー
- 心の記録
- 社会と法
- メンタル・マインドセット
- 日常と非日常の狭間
📖 目次
- 明日は裁判——その言葉が持つ重み
- 簡易裁判所へ行くということ
- 不安という名の静かな波
- 「淡々と話す」ことの難しさ
- 初公判、沈黙の時間の中で
- 法という舞台に立つ個人として
- 終章:それでも明日はやってくる
✍️ 本文
1. 明日は裁判——その言葉が持つ重み
「明日は裁判だ。」
その言葉を口にするたびに、少しだけ胸の奥が重たくなる。
それは、怒りでも恐れでもない。
ただ、“現実”が静かにそこに立ち上がる音のようなものだ。
人生の中で「裁判」という言葉に触れる機会は、そう多くない。
テレビの中の出来事、ニュースの向こう側の話。
けれど、明日、その「法廷」という現場に自分が足を運ぶことになる。
それだけで、空気の重さが変わる。
裁判という言葉には、
“白黒をつける”という明快さと、
“人の思いが交錯する”という曖昧さが、同時に宿っている。
その狭間で、私は今、深呼吸をしている。
2. 簡易裁判所へ行くということ
場所は「簡易裁判所」。
ニュースで聞くような大きな法廷ではない。
けれど、“簡易”とはいえ、そこには立派な法の場が広がる。
入口を入ると、金属探知機と無機質な白い壁。
裁判所特有の、静かで、時間が少し止まったような空気がある。
そして、**そこにいる全員が「何かを抱えている人たち」**だ。
訴える人、訴えられる人、傍聴に来た人、職員、弁護士。
誰もが、何かを背負って、その場所に来ている。
明日は、私もその一人になる。
3. 不安という名の静かな波
正直に言えば、不安はある。
でも、それはパニックのような強烈なものではなく、
静かに押し寄せる波のような不安だ。
「ちゃんと話せるかな」
「変に誤解されないだろうか」
「結果はどうなるのだろう」
頭の中を巡る問いの数々。
けれど結局、その答えは明日しか分からない。
人間は、未知の出来事を前にしたとき、
不安を感じるようにできている。
だから今、この気持ちも自然なものとして受け入れる。
4. 「淡々と話す」ことの難しさ
「思っていることを、淡々と喋るだけ。」
簡単なようでいて、実はとても難しい。
感情を抑えながら、事実だけを伝える。
冷静さを保ちながら、自分の主張をする。
それは、感情を消すというよりも、感情を整える作業だ。
人前で自分の出来事を話すとき、
どうしても言葉には“心”がにじむ。
その心が誠実であればあるほど、
ときに、うまく伝わらないこともある。
けれど、明日はそれでいい。
淡々と、事実を語る。
それが一番の誠実さだと思っている。
5. 初公判、沈黙の時間の中で
初公判は、ほとんど“話す機会がない”ことも多い。
それでも、法廷という空間に自分の存在を置くということには意味がある。
静まり返った法廷、響く書記官の声、
机に置かれた書類の音、
小さな咳払い——。
そのすべてが、**「現実の重さ」**を教えてくれる。
沈黙の中で、私は何を思うのだろう。
怒りでも、悲しみでもなく、
ただ、**「これもまた人生の一部なのだ」**と受け止めたい。
6. 法という舞台に立つ個人として
裁判というのは、誰かを責めるためのものではない。
正義のための戦いでもない。
それは、**「真実を整理するための時間」**だ。
法廷は、まるで舞台のように整然としている。
だが、そこで演じるのは、役ではなく「現実」だ。
そしてその現実の中心に、
私は“個人”として立つ。
守るものも、恐れるものも、背負うものも、全部背中に抱えながら。
7. 終章:それでも明日はやってくる
不安な夜は、長く感じる。
でも、夜明けは必ずやってくる。
明日、裁判所の前に立ったとき、
きっと私は少しだけ背筋を伸ばしているだろう。
結果がどうであれ、
その場に立つという経験は、
これからの人生で、確実に何かを変えてくれる。
「明日は裁判」
——そう思える自分を、
今夜だけは静かに、褒めてあげたい。


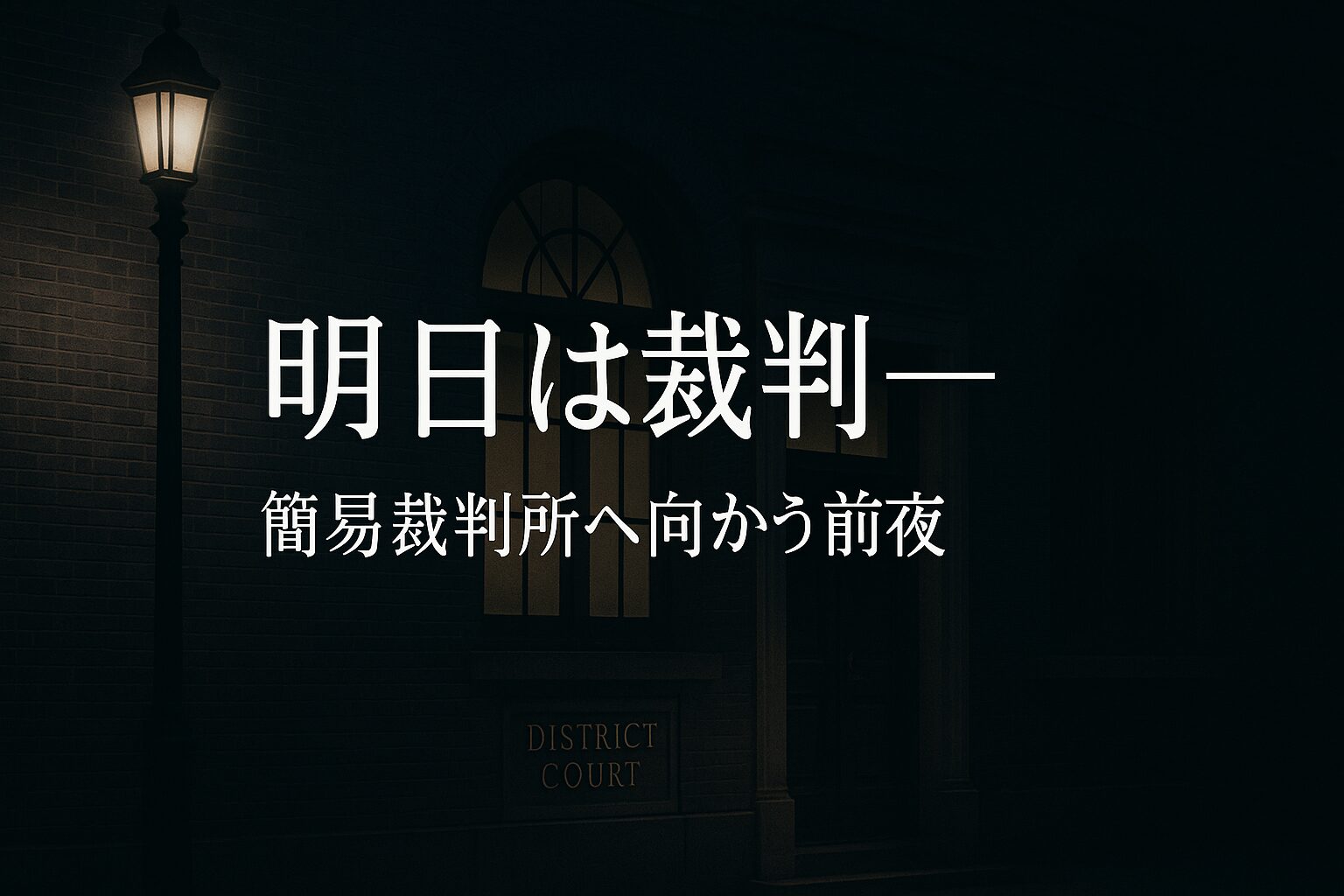
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=18469214&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2602%2F9784535522602.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)