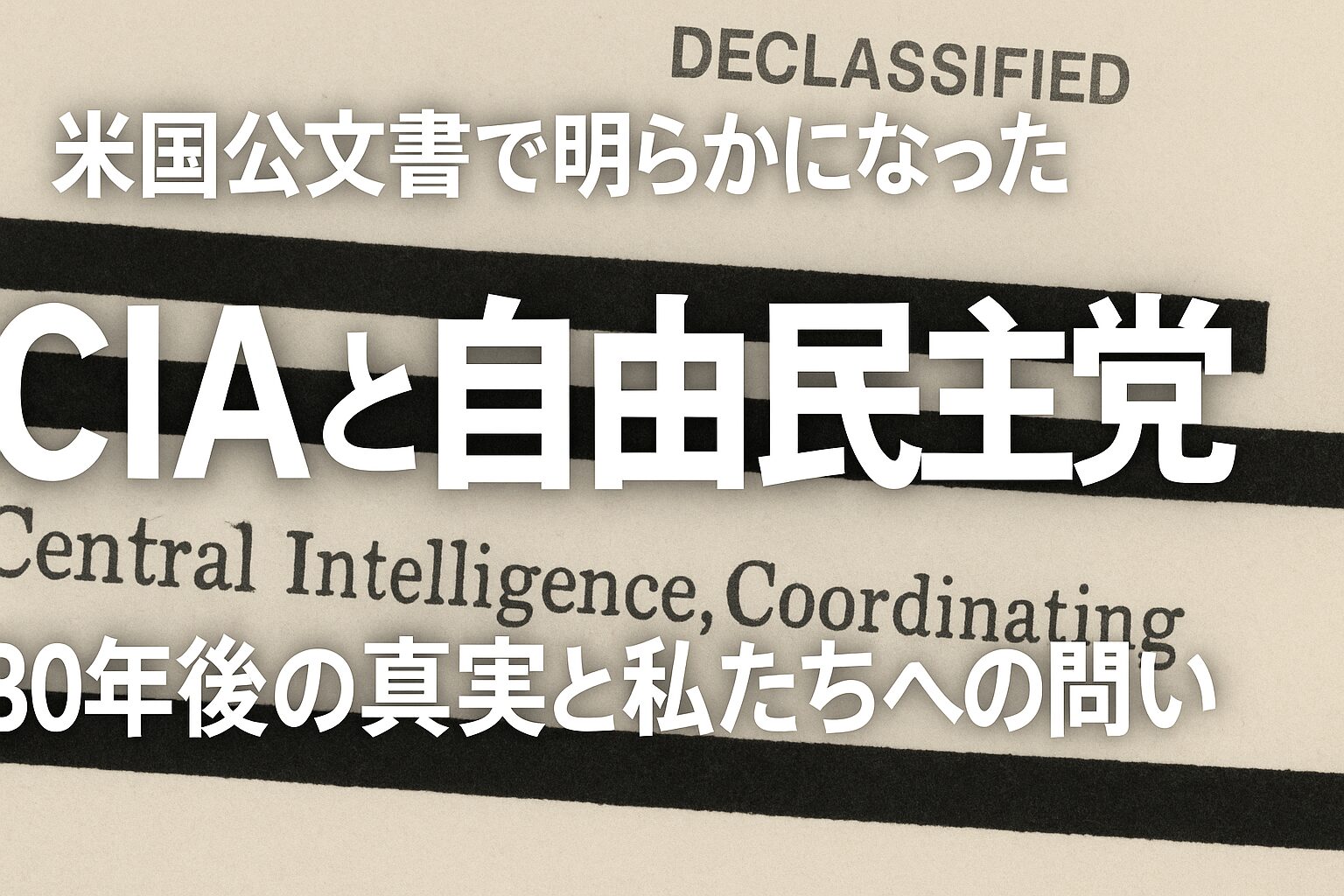消費税はなぜ廃止できないのか? スーパーの買い物から考える生活実感とスタグフレーションの影
1. 今日の体験から見える「物価の壁」
今日はスーパーに買い物に行った。
「インフレ率は3%前後」というのが公式な数字だが、レジで支払いをする瞬間、その言葉は現実味を失う。
むしろ実感としては、20%以上の値上げが進んでいるように思える。
例えば日用品、パン、調味料、さらにはちょっとしたデザートやアイスまで。
以前なら気軽に買えていたものが、いまは「我慢しよう」という対象に変わってしまった。
結果として、私はアイスを買うのを辞めた。
健康には良いかもしれない。少しは痩せるきっかけになるかもしれない。
だが、これは本来、前向きな理由で消費を減らすのではなく、物価高で消費を制限しているという現実だ。
2. 消費税はなぜ廃止されないのか?
こうした状況でよく議論になるのが「消費税を下げればいいのではないか?」という話だ。
とくに、消費税を廃止することで家計にゆとりを与え、需要を喚起する効果が期待される。
消費税の特徴
- 所得に関係なく一律に課税される → 低所得者ほど負担感が大きい
- 生活必需品にもかかる → 毎日の食費・日用品が確実に値上がり
- 景気が悪いときにも一定の税収がある → 政府にとって安定財源
この「政府にとって安定的」という点が、最大の理由だろう。
財政赤字が深刻な日本では、消費税は「なくせない税」とされている。
だが裏を返せば、生活者を直撃する税でもある。
だからこそ「いまのように景気が弱いときに課税するのは逆効果では?」と考える人が多い。
3. スタグフレーションの影
現在の日本経済は、典型的なスタグフレーションの兆候を見せている。
- **インフレ(物価高)**は進む
- 賃金は思うように上がらない
- 景気は停滞気味
これこそが「生活は苦しいのに値段だけ上がる」という感覚の正体だ。
米国はエネルギー・IT産業の強さやドル基軸通貨の力でまだ対処できる。
だが日本は「輸入依存度が高く」「少子高齢化で需要が縮小」しているため、
より深刻に生活に跳ね返ってきている。
4. 日銀と利上げのタイミング
さらに問題なのは、金融政策だ。
利上げのチャンスを逃し続けてきた日本銀行は、
「いまから利上げをしても景気を冷やすだけ」という難しい状況に陥っている。
本来なら、景気が少し回復しているときに金利を引き上げ、
その余地を残しておくべきだった。
しかし長く続いたゼロ金利政策が、日本を動けなくしてしまった。
今後、円安がさらに進み、輸入物価が上昇すれば、
スタグフレーションはさらに深刻化するだろう。
5. 生活者としてできること
では、私たちはどうすればよいのだろうか?
(1)消費の優先順位を整理する
- 本当に必要なものに絞る
- 「ご褒美消費」を週に1回だけにするなどルールを作る
(2)健康面でのプラスに転換する
- アイスを買わない → 摂取カロリーを減らせる
- 自炊を増やす → 外食より安く、健康的
(3)声を上げる
- 消費税減税や生活支援策について、議論を広げる
- SNSや地域コミュニティで「生活実感」を共有する
6. 結論:「小さな買い物」から見える大きな課題
スーパーでの買い物。
アイスひとつを買うかどうかで悩む日常。
その背後には、日本経済全体のゆがみが存在する。
- 消費税という逆進性の強い税制度
- スタグフレーションという生活を圧迫する現象
- 利上げできない日銀という制約
この三重苦が、いまの私たちの暮らしに影を落としている。
だからこそ、単なる「愚痴」や「節約術」だけでなく、
社会全体の課題として考えていくことが必要だ。
私が今日アイスを我慢したこと。
その小さな選択は、もしかすると「日本社会の縮図」なのかもしれない。
まとめ
- 公式発表の3%インフレではなく、生活実感は20%以上
- 消費税は生活者を直撃するが、政府は安定財源として手放せない
- 日本は典型的なスタグフレーションに直面している
- 日銀は利上げのタイミングを逃し、動けない状況にある
- 生活者としては「消費の優先順位」「健康志向」「声を上げること」が重要



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/278dfe1a.1dbb1f6b.278dfe1b.f0520962/?me_id=1213310&item_id=21692136&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1314%2F9784295411314_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)